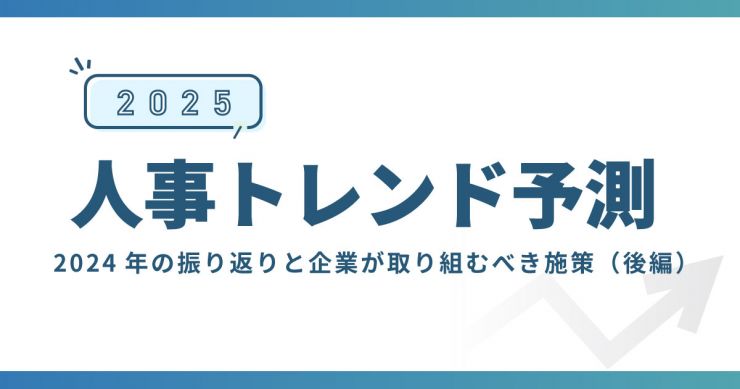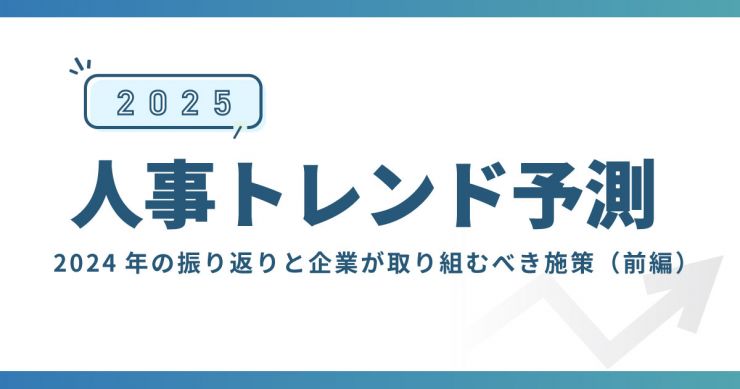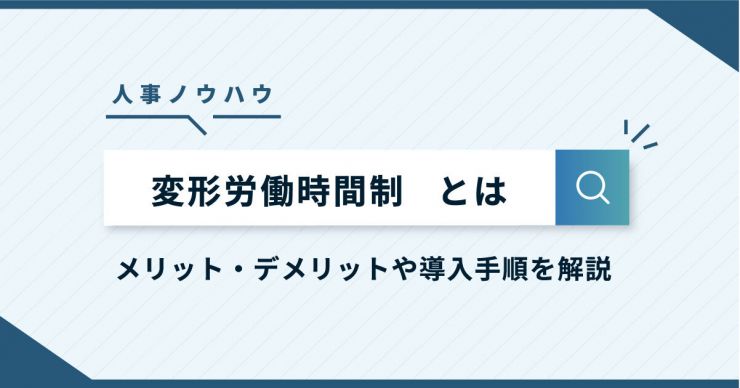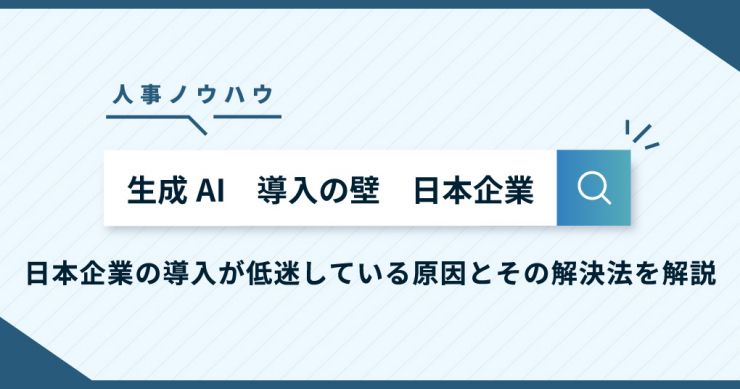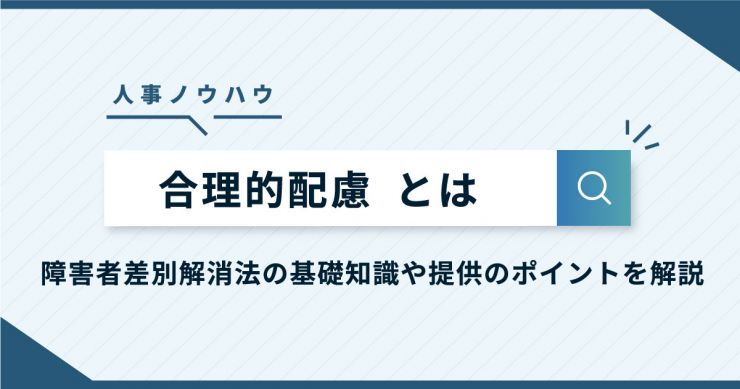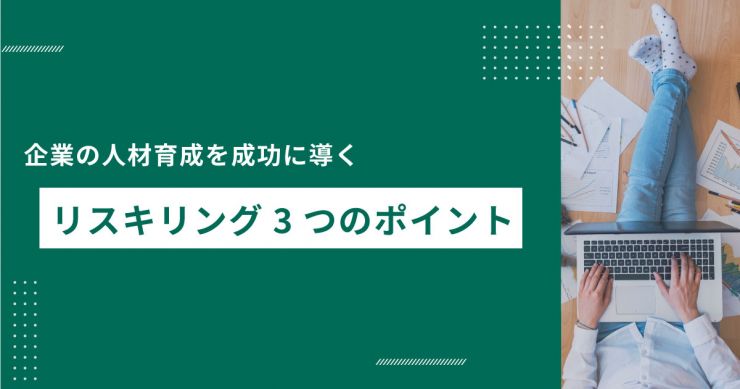前編では、2024年の人事トレンド4つについて、企業の取り組みや課題、今後の見通しについて詳しく解説しました。
本記事の後編は、2025年に人事部門が押さえておくべきトレンドについてご紹介します。①育児・介護休業法の改正、②賃上げの実施、③生成AI活用、④障がい者雇用、⑤スキルベースの人材マネジメントの5つにフォーカスして、注目される理由、その背景と企業が実施すべき実務対応のポイントについて詳しく解説します。
1分サマリ
①育児・介護休業法の改正
育児・介護休業法改正の施行に向けて、就業規則や労使協定の改訂、個別聴取への対応等が求められる。
②賃上げの実施
賃上げは人手不足が深刻な業界や資金に余裕のある企業に限定されるとみられる。
③生成AI活用
生成AIではマルチモーダルAIや業務特化型AIの普及が予想される。
④障がい者雇用
障がい者雇用では採用・定着・配属先の受け入れ、3つの観点で企業の対応が必要。
⑤スキルベースの人材マネジメント
スキルを軸にした人材マネジメントでは「ポータブルスキル」と「自社固有スキル」に分けて自社に必要なスキルを定義することが重要。
1. 育児・介護休業法の改正
2024年に発表された最新(2023年)の合計特殊出生率は過去最低を更新しました。さらに、2025年には団塊の世代が75歳以上となり、医療や介護の需要が急増することが懸念されています。この問題は「2025年問題」として知られ、社会的な課題として注目されています。
こうした背景を受け、国は育児と介護の両立支援に向けて、休暇の取得を促進する施策や、テレワークの努力義務化などを盛り込んだ育児・介護休業法の改正を予定しています。
育児関連の施行内容
育児を行う労働者の離職率を下げるため、育児と仕事を両立しやすい環境を作ります。施行内容は以下の通りです。
【2025年4月施行】
| 制度 | 改正内容 | 施行前 | 施行後 |
|---|---|---|---|
| 子の看護休暇 ※施行後は子の看護等休暇 |
子の範囲の拡大 | 小学校就学の始期に達するまで | 小学校3年生修了まで |
| 取得事由拡大 | ①病気・けが ②予防接種・健康診断 |
①病気・けが ②予防接種・健康診断 (追加) ③感染症に伴う学級閉鎖等 ④入園(入学)式、卒園式 |
|
| 労使協定による除外規定の一部廃止 | ①週の所定労働日数が2日以下 ②継続雇用期間6か月未満 |
①週の所定労働日数が2日以下 ※②を撤廃 |
|
| 所定外労働の制限(残業免除)の請求 | 対象労働者が養育する子の範囲拡大 | 3歳未満の子 | 小学校就学前の子 |
| 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置 | 代替措置追加 | ①育児休業に関する制度に準ずる措置 ②始業時刻の変更等 |
①育児休業に関する制度に準ずる措置 ②始業時刻の変更等 (追加) ③テレワーク |
| テレワーク | 創設 | ー | 3歳未満の子を養育する労働者に対するテレワーク導入(努力義務) |
| 育児休業取得状況の公表義務対象企業 | 義務対象企業拡大 | 従業員数1,000人 | 従業員数300人超 |
(参考)厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
【2025年10月施行】
・3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、事業主は以下5つの措置の中から、2つ以上の措置を準備し、労働者がそのうち1つを選択可能になる。
| 柔軟な働き方を実現するための措置 | 備考 |
|---|---|
| ① 始業時刻等の変更 | フレックスタイム制または始業、終業における時差出勤 |
| ② テレワーク等(10日以上/月) | ・PCを使用しない在宅勤務やサテライトオフィスでの勤務を含む ・原則時間単位で取得可 |
| ③ 保育施設の設置運営等 | 「等」にはベビーシッターの手配、費用補助がある(カフェテリアプランのメニューでも可) |
| ④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年) | 養育両立支援休暇とは3歳から小学校就学前の子を養育する労働者が就学予定の小学校の下見等、子の養育に資するものであればいかなる目的でも使用可能な休暇 |
| ⑤ 短時間勤務制度 | ー |
・労働者本人や配偶者の妊娠・出産時、また子の3歳の誕生日1ヵ月前までの1年間に、勤務時間帯や勤務地等の働き方に関して、個別に意向を確認し、配慮する。
介護関連の施行内容
介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度を強化するために、以下の内容が施行されます。
【2025年4月施行】
・継続雇用期間6か月未満の従業員に対し、労使協定によって介護休暇の対象外とする規定を撤廃。
・介護両立支援制度に関する研修の実施や相談窓口の設置等、介護離職防止のための雇用環境整備を義務化。
・介護に直面した旨の申出をした労働者に対し、制度に関する個別の周知、制度利用の意向確認を行うことを義務化。
・介護に直面する前の早い段階(40歳到達付近)を迎えた従業員に対して、介護両立支援制度や申し出先等に関する情報提供を行うことを義務化。
・要介護状態の対象家族を介護する従業員に対して、テレワーク可能な体制を導入することが努力義務となる。
(参考)厚生労働省 トピックス「育児・介護休業法が改正されました ~令和7年4月1日から段階的に施行」
://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」
育児・介護休業法改正において企業が取り組むべきポイント
企業が実施すべき実務対応のポイント
今回の育児・介護休業法の改正に対応するにあたって、規定の整備や業務フローの策定等、企業は以下の対応が求められます。
・労使協定の改訂
労使協定によって継続雇用期間6か月未満の従業員について子の看護休暇や介護休暇の対象外としている場合は、労使協定の改訂が必要になります。
・就業規則の改訂
子の看護休暇の見直しや柔軟な働き方を実現するための措置等については、従業員がその制度を法律に基づいて利用できる就業規則へ改正する必要があります。
・個別の聴取の業務フロー策定と運用
育児、介護ともに従業員への制度の周知、意向確認、情報提供が必要になります。対象労働者のリストアップ、聴取を誰が実施するか、聴取した内容をどのように保存するか等業務フローを策定しておく必要があります。
・テレワークができる環境整備
テレワーク可能な体制の導入はあくまで努力義務ですが、実施する際にはテレワークを許可する就業場所(自宅やレンタルオフィス等)や労働時間の管理方法を就業規則に定める必要があります。
また情報漏洩リスクや通信のセキュリティリスクに関する対策も検討しなければなりません。
従業員の満足度をさらに高めるためのポイント
前項で紹介したポイントはあくまで最低限の対応です。
今回の法改正対応をきっかけに、子育てあるいは介護をする従業員が自社で働き続けるために、どんなことが必要なのか、改めて議論をするきっかけにしてもよいのではないでしょうか。法律の内容を上回る制度にしたり、上記で示された休暇の取得やテレワーク以外に自社独自の措置を実施してもまったく問題はありません。
人手不足が深刻化する中で、企業にとって従業員の離職防止や新たな人材採用も重要な課題です。子育てや介護をしやすい環境があるかどうかが、企業を選ぶ要素の一つになる場合もあります。
単に法律に合わせるだけでなく、従業員の満足度向上と採用力向上のために福利厚生を充実させることが、自社にとって中長期的なメリットになります。
法改正対応や自社の福利厚生を充実させるために、従業員がどのような制度を求めているのか、また育児や介護で何に困っているのか、ヒアリングやアンケート調査を実施してもよいでしょう。
従業員の意向聴取や相談窓口の設置も、単に形式的に実施すればよいというものでもありません。重要なのは従業員にとって制度が利用しやすいように運用することです。たとえば休暇を取得しやすいように、人事部が積極的に業務の引継ぎや周囲の理解を促進し、従業員の心理的安全性を高めることも必要です。
2. 賃上げの実施
賃上げが2025年に注目される背景
2023年、2024年には賃上げの大きな波がありました。2025年もその波が継続するのかどうか、企業の動向が注目されていますが、2025年の賃上げは、人手不足の問題が大きい業界や業績が好調な企業に限定されると予想しています。
人手不足が深刻な業界の例として、小売業界や飲食業界が挙げられます。これらの業界では、店舗の人材採用力を強化するために、賃上げを表明する企業が増えてきています。
2023年、2024年には物価高への対応として、多くの企業が賃上げを発表しました。しかし、2年連続で賃上げを行った企業では、人件費の負担が大きく増加しています。2025年にさらに賃上げを実施できる企業は、業績が好調であるか、資金に余裕のある企業に限られると予想されます。
賃上げにおける企業が取り組むべきポイント
2025年の賃上げは2023年、2024年よりも慎重に判断する必要があります。業界によっては採用競争力維持のため、賃上げが相次ぐことも想定されますが、自社の財務状況がそれに耐えられるかどうかを見極めなければなりません。
特にベースアップをした場合、一度上げた基本給を下げるためには、労働組合との交渉が必要になります。将来の業績と人件費負担をシミュレーションして賃上げするかどうか決定しましょう。また一律ではなく、賞与や手当で一部の従業員のみ賃上げすることも選択肢の一つです。
3. 生成AI活用
生成AIが2025年に注目される背景
生成AIは今、かつてない速度で進化しています。この技術は、単なる情報処理ツールではなく、戦略的な意思決定や人材管理における新しい可能性を切り拓いています。
本章では、2025年を見据えた生成AIの潮流とHR分野での実務的な応用例を整理し、具体的な活用施策をご紹介します。
生成AIがもたらす3つの変化
生成AIの進化がもたらす2025年のHRトレンドは、次の3つの側面で大きな影響を与えると考えられます。
1. モデルの強化
生成AIモデルのパラメーター数が増加することで、タスク遂行能力がさらに高まります。これにより、人材データの解析や予測の精度が向上し、退職リスクの予測や適材適所の配置といった、従来は困難だった領域でも実用化が進むと予想されます。
2. マルチモーダルAIの普及
テキストだけでなく画像や音声等、複数のデータを統合的に処理する能力が発展します。たとえば、ビデオ面接の映像や音声データを解析し、候補者の非言語的特徴やコミュニケーション能力を評価する採用プロセスが現実のものとなるでしょう。
3. 業務特化型ツールの普及
小規模な生成AIモデルが特定業務に最適化され、勤怠データの分析やFAQ対応の自動化など、現場で直ちに効果が出るソリューションが普及すると予想されます。
生成AIにおける企業が取り組むべきポイント
これらの潮流を受けて、人事部門が取るべき具体的な対応策を3つ紹介します。
1. 小さく始めるPoC(実証実験)
生成AIをいきなり大規模に導入するのではなく、まずは小さな課題に絞ったPoCから始めることをおすすめします。たとえば、勤怠データを活用した退職リスクの予測を試験的に運用してみると、生成AIの有効性を具体的に実感できるかもしれません。
2. データ統合の基盤整備
生成AIの効果を最大化するには、人事部門に散在するデータを統合的に管理する基盤が必要です。スキルデータや勤怠情報、評価データ等を横断的に活用することで、より精度の高い意思決定が可能になります。
3. 社内リテラシーの向上と外部リソースの活用
生成AIを活用するには、技術への深い理解が欠かせません。現場の担当者から経営層まで、生成AIの可能性と限界を正しく理解するためのトレーニングを推進しましょう。
また、外部の専門家やパートナーを活用することで、導入のハードルを下げることも重要です。
4. 障がい者雇用
障がい者雇用が注目される背景
法定雇用率の引き上げと人手不足の2つの要因から障がい者雇用に注目が集まっています。
身体障がい者の雇用数が頭打ちになる中で、事業者は精神障がい者や知的障がい者の雇用を進めようとしていますが、採用や定着、配属先の受け入れ等に課題を感じているようです。
障がい者雇用における企業が取り組むべきポイント
・採用
障がい者を採用する際は日常生活に関する基盤や支援体制が整えられていること、そして就労を開始した後の配慮事項を確認することが重要です。また、面接だけでは測れないスキル、得意不得意の把握をかねて、インターンシップのような形で就業体験を行うことも有効です。
・定着
障がい者の場合、定着率の低さも課題となっています。2024年4月1日から改正障がい者差別解消法が施行され、民間企業にも合理的配慮の提供が義務化されました。
特に障がい者から配慮の申し出があった際には、建設的な対話を行う義務があり、可能な範囲で申し出に応じなければなりません。
このような法的要件があるため、定期的に人事担当者やジョブコーチの資格を持つ者が「就業における困りごと」をヒアリングすることが有効です。
・配属先の受け入れ
障がい者が実際に就業する配属先の上長や同僚が、障がい者本人の特性について理解を深めることで、離職防止につながります。
タレントマネジメントシステムを活用してプロフィールシートを作成し、障がい者本人の希望に応じてシートの一部を配属先の上司、同僚に見せながら、当事者同士で働きやすい環境を模索していくことが望ましいでしょう。
5. スキルベースの人材マネジメント
スキルを軸にした人材マネジメントが注目される背景
アメリカを中心にスキルベースの人材マネジメントが注目されています。
スキルベースとは、複数の人材のスキルを組み合わせることでジョブ要件を満たすという考え方に基づく人材マネジメントの手法です。
人材不足時代において、ジョブに応じたスキルを持つ人材の獲得や維持が難しくなっていることから、このような人材マネジメントが注目されています。
日本では職能等級制度をベースにした人材マネジメントが行われてきましたが、2020年以降、「ジョブ型」への移行が進む企業もみられます。
近年、アメリカでのトレンドを背景に、従来の欧米のジョブ型とは異なり、スキルを組み込んだ人材マネジメントにも関心が高まっています。
スキルベースの人材マネジメントにおける企業が取り組むべきポイント
スキルベースの人材マネジメントで重要なのは「自社に必要なスキルの定義」です。
一般的なビジネススキルや業界内で通用するスキルである『ポータブルスキル』と、自社の特色に強く結びつき、キャリア形成にも関連する『自社固有スキル』の種類を考慮し、さらに各スキルのレベル(習熟度や熟練度)を見極めることが重要です。
なお、従業員が現在持っているスキルを調査して自社に必要なスキルを定義する方法もありますが、この方法を採用する場合、以下の2点に留意する必要があります。
1. 従業員が協力するためのメリットを提示する
希望部署への異動や昇給・昇格に関連させるなど、従業員側のメリットを打ち出すことで、自身の保持スキル情報を提供することに協力してもらいやすくなるでしょう。
2.将来必要なスキルやレベルも考える
現在の従業員が持っているスキルは、あくまで現在の業務で使用しているスキルが中心です。しかし、組織は『3か年計画』などの将来の成長を見据えた計画を立てるため、その計画に沿ったスキルやレベルの定義が必要です。
スキルの種類やスキルレベルを明確にするには、タレントマネジメントのパッケージシステムが役立ちます。システムには、国内外のさまざまな組織で定義されたスキルの種類やレベルが集合知として用意されており、自社で必要なスキルとの照合に役立ちます。
さいごに
2025年は法改正施行への対応に加えて、賃上げやさらに進化する生成AIへの注目が続くと予想されます。そしてより障がい者が働きやすい社会の実現に向けて、企業にも協力が求められます。新しいトレンドであるスキルベースの人材マネジメント動向からも目が離せません。
トレンドを追いつつ、自社ではどのような取り組みを行っていくのか、方針を考えるために本記事が参考になれば幸いです。