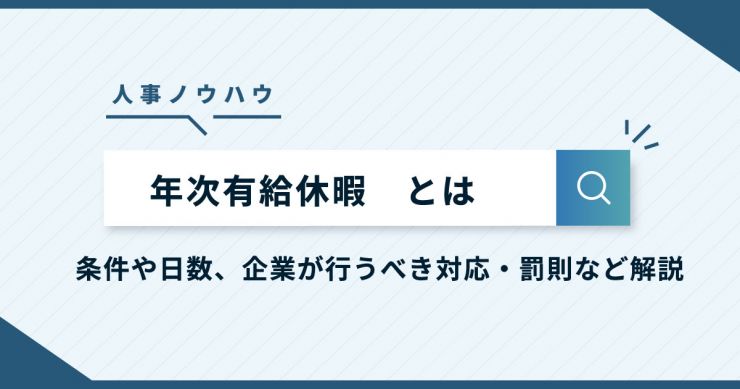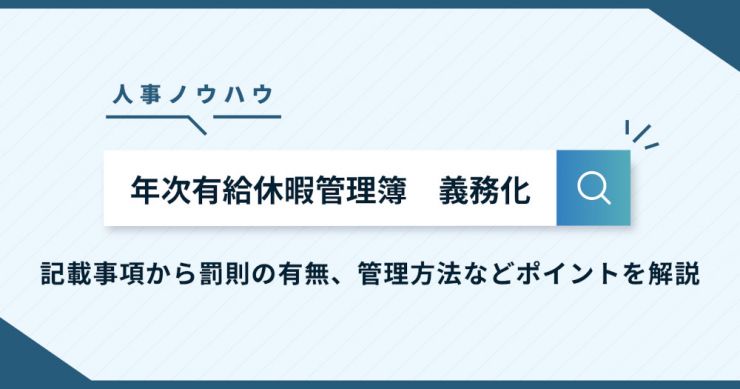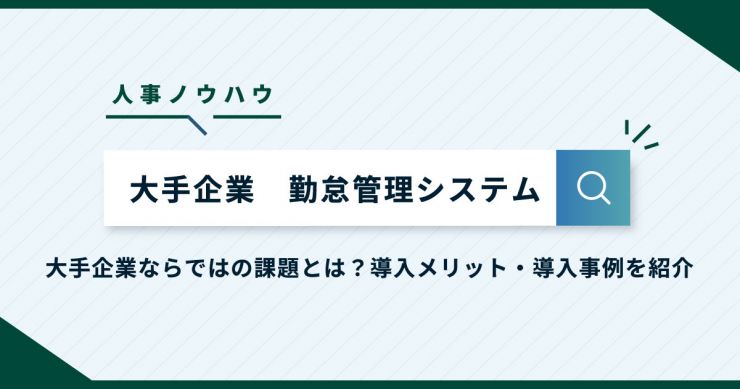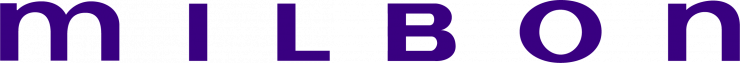有給休暇の適切な管理と取得は、法令順守だけでなく従業員の働きやすさや企業の信頼性にも関わります。
本記事では、有給休暇制度の基本、現場で起こりがちな課題、システムを活用した効率化の方法、そして取得率向上によるエンゲージメントや企業価値向上まで、事例を交えてご紹介します。
目次
有給休暇制度の基本
有給休暇制度は、企業にとって法令順守と従業員満足の両面で重要です。正しく理解し、適切に管理することは、リスクを防ぐだけでなく、働きやすい職場づくりにも繋がります。
有給休暇制度とは?
有給休暇は、労働基準法で定められた労働者の権利であり、企業はその付与・管理に関して法的な責任を負っています。正社員はもちろん、所定の条件を満たすパートタイム・アルバイト労働者にも付与しなければいけません。
「年次有給休暇」「年休」など、様々な呼び方があります。基本的には「有給休暇制度」と同じ意味です。
有給休暇が付与される要件
原則、以下2点を満たす場合、年10日の有給休暇が付与されます。
・雇い入れ日から6か月継続勤務していること
・その期間の出勤率が8割以上であること
その後は、次のように勤続年数に応じて有給日数が増加し、最大で年20日が付与されます。
①原則となる付与日数
| 継続勤務年数 | 6か月 | 1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
出典:厚生労働省 「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」①原則となる付与日(P3)
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
なお、所定労働日数が少ないパートタイム・アルバイト労働者には、有給休暇が出勤日数に応じて比例付与されます。
対象となるのは、「週の所定労働時間が30時間未満」であり、かつ「週の所定労働日数が4日以下」または「年間の所定労働日数が216日以下」の労働者です。
②パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数
| 週所定 労働日数 |
1年間の所定 労働日数 |
継続勤務年数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6か月 | 1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月以上 |
|||
| 4日 | 169日~ 216日 |
付 与 日 数 |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121日~ 168日 |
5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
| 2日 | 73日~ 120日 |
3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
| 1日 | 48日~ 72日 |
1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | |
出典:厚生労働省 「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」②パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数(P3)
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
(※)表中赤文字部分に該当する労働者は、2019年4月から義務付けられる「年5日の年次有給休暇の確実な取得」の対象となります。
企業が知っておくべき改正労働基準法の内容
2019年の労働基準法改正では、企業に対し有給休暇の取得管理に関する新たな義務が課されました。中でも重要なのが、「年5日の有給休暇取得義務」と「年次有給休暇管理簿の作成・保存義務」です。それぞれどのような義務か、解説します。
<年5日の有給休暇取得義務、罰則>
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、企業は毎年5日以上を必ず取得させる義務があります。この義務は、正社員だけでなく週4日以下のパート・アルバイトにも適用されます。
取得が行われない場合、企業側に責任があり、30万円以下の罰金を科される場合があるので気をつけましょう。
<年次有給休暇管理簿の作成・保存義務>
企業は労働者ごとに、有給休暇の基準日・付与日数・取得日などを記載した「年次有給休暇管理簿」を作成・管理しなければなりません。
この管理簿は、取得期間の終了後3年間(付与日から3年)保存することが義務付けられています。
有給休暇の繰り越し・時効ルール
有給休暇には付与日から2年間の時効が定められており、未取得分は翌年度に限り繰り越し可能です。たとえば、2023年4月1日に付与された有給休暇は、2025年3月31日までに取得しなければ、時効により消滅します。
この「繰り越しルール」は労働基準法に基づくものであり、正しく運用しないと法令違反に繋がる可能性があります。また、「新たに付与された有給休暇」と「前年度からの繰り越し分」のどちらを先に消化するかについて、労働基準法では明確な優先順位が定められていません。
実務では、時効による消滅を防ぐために、繰り越し分から優先的に消化する方法が一般的です。ただし、企業の就業規則において「新規付与分から先に消化する」と定めている場合は、そのルールに従うことになります。
積立休暇と有給休暇の違い
有給休暇は、労働基準法で定められた制度で、原則としてその年度内に取得する必要があります。
一方、積立休暇は、法的な定めが特にないため企業での実施は任意であり、失効した年次有給休暇を積み立てて、より長期的な休暇を取得できる制度です。
有給休暇の取得促進のメリット
有給休暇の取得促進は、法令遵守にとどまらず、従業員のエンゲージメント向上や企業の競争力強化に直結します。企業へのメリットは大きく4点です。
1. 離職率低下と人材定着
有給休暇を安心して取得できる環境は、従業員の満足度や信頼感に直結します。結果として、離職率の低下や人材の定着に繋がり、採用・育成コストの削減にも貢献します。
特に若手社員や育児・介護などの制約を持つ従業員にとっては「休みやすさ」が企業選びの重要な判断軸となるため、休暇の取りやすさは人材戦略の重要な土台となるでしょう。
2. 自律的な働き方の促進
取得しやすい環境を整えることで、従業員は自身のライフスタイルや体調に合わせて自律的に休暇を取得しやすくなります。これは単なる福利厚生の充実にとどまらず、仕事の生産性や集中力の向上にも繋がります。
組織としても、自律性を尊重する風土が育ち、業務の効率化や主体的な行動を促す文化醸成のためにも重要です。
3.「休みやすさ」が採用競争力を左右する時代
近年、求人票の「休暇制度の実態」は、求職者にとって重要なポイントです。制度があっても取得しにくい職場環境では、企業の魅力は下がってしまいます。
有給取得率を高め、その実績を「見える化」に企業として取り組むことは、働きやすさをアピールする強力な材料となり、採用競争力の強化に直結します。
4. エンゲージメント向上、企業価値の向上に繋がる
企業が従業員の働きやすさに取り組み、有給休暇の取得実績や管理体制を公開することは、株主や取引先、社会全体からの信頼獲得にも繋がります。
人的資本の情報開示が注目される中、こうした取り組みはESG経営やサステナビリティの観点からも価値あるものとして評価されます。従業員のエンゲージメントを高めることは、企業の長期的な成長戦略の一環ともいえるでしょう。
企業が抱える、有給休暇管理の課題やよくあるお悩み
有給休暇制度について労使協定や就業規則を整備していても、実際の運用では多くの企業が課題を抱えています。ここでは、現場でよく見られる課題とその背景を3つの観点から整理します。
1. 手作業による有給休暇の付与ミス・計算漏れ
有給休暇は、従業員の勤続期間や労働日数に応じて正確に付与する必要がありますが、表計算ソフトや紙の台帳などで手作業管理をしていると、以下のようなリスクが生じやすくなります。
・ 計算ミス・付与漏れによる法令違反リスク
・ 勤続年数に応じた自動更新・時効管理の業務負担増
・ 担当者の引き継ぎや属人化による運用の不安定化
特に、年5日取得義務の対象者特定と取得管理をミスすると、罰則リスクも伴います。
2. 取得状況の可視化ができていない
労働基準法上、企業はすべての労働者について「年次有給休暇管理簿」を作成・保存する義務があります。しかし実際には、次のような理由で可視化が不十分なケースも少なくありません。
・ 紙・表計算ソフトによる管理のため記録更新が後回し
・ 担当者の人手不足によりデータ整備が追いつかない
・ 管理簿未整備による取得実態の把握不能化
こうした状況が続くと、有給取得率の低下だけでなく、従業員の満足度やワークライフバランスにも悪影響を与えかねません。
3. 有給休暇の取得管理が「自己責任」になっている
企業によっては、有給休暇の取得が従業員任せ(自己申告)になっているケースがあります。この場合、以下のような問題が起こりやすくなります。
・ 上司や管理者からの取得促進がない
・ リマインド通知がなく、申請し忘れる
・ 残日数がわからず取得をためらう
結果として、従業員の取得率が伸びず、「年5日の取得義務」に対応できないリスクが高まります。有給管理の主体は企業側にあることを再確認し、適切なフォロー体制が必要です。
システム活用による有給休暇管理の効率化しよう
有給休暇を適切に管理するには、法令の遵守だけでなく、属人的な運用によるミスの防止や、業務効率の向上、従業員の取得意識の醸成など、多面的な配慮が必要です。こうした課題に対応する有効な手段が、勤怠管理システムの導入・活用です。
1. 勤続期間や入社月に応じた休暇の自動算出・付与
勤続年数や入社月に応じて有給休暇を自動付与できるシステムを導入することで、計算ミスや漏れを防ぎながら、法令を確実に遵守できます。
特に、中途入社者や時短勤務者など、付与条件が複雑になりやすいケースでも、システムに自動算出の機能があれば、より担当者の業務負荷を軽減できます。また、従業員自身も付与日数を明確に把握できるようになるため、制度運用の透明性と信頼性も向上できます。
2. 休暇の残数・使用数・申請数をリアルタイムで確認
従業員と管理者の双方が、有給休暇の残日数や取得実績をリアルタイムで確認できる環境を整えることで、申請や承認がスムーズになり、従業員は計画的な取得がしやすくなります。
また、従業員ごとの取得状況が見えることで、年5日の取得義務への対応状況も明確になり、企業側の管理責任も果たしやすくなります。
3. 通知・アラート機能で労務管理の漏れを防ぐ
取得期限が近づいた従業員に自動で通知を送ったり、管理者に対して未取得者リストを提示したりするアラート機能に対応したシステムは有給休暇の取得促進に有効です。
手間なく従業員にリマインドできるしくみは、担当者の工数削減だけでなく、現場管理者の実効性を高める手段としても注目されています。こうした機能の活用は、取得漏れを防ぎ、法令違反のリスクを大きく低減します。
システム活用による有給管理の効率化事例:株式会社ミルボン様
美容室向けヘア化粧品メーカーの株式会社ミルボン様では、有給休暇の取得状況や時間外労働の管理が煩雑で、業務改善にも活かしきれていないという課題を抱えていました。
こうした背景から、同社ではクラウド勤怠管理システム「COMPANY 就労・プロジェクト管理」を導入しました。これにより、部門ごとの有給休暇取得率をはじめとした様々な勤怠指標の見える化を実現し、業務管理の効率化と働きやすい環境づくりを推進されています。
詳細は株式会社ミルボン様の導入事例記事をご覧ください。勤怠管理での課題や、導入効果について記載しています。
有給管理を正しく、効率的に
本記事では、有給休暇制度の基本から、企業が押さえておくべき改正労働基準法の内容や、注意ポイントなどを解説しました。
有給休暇の取得促進は、従業員の離職率低下、自律的な働き方の促進、採用競争力の向上、ひいては企業価値の向上に繋がる重要な要素です。
しかし、多くの企業では手作業による付与ミスや計算漏れ、取得状況の可視化不足、従業員任せの管理といった課題を抱えています。これらの課題を解決し、法令遵守と業務効率化を両立させるためには、勤怠管理システムの活用が有効です。有給管理を正しく効率的に行い、働きやすい職場環境の実現を目指しましょう。