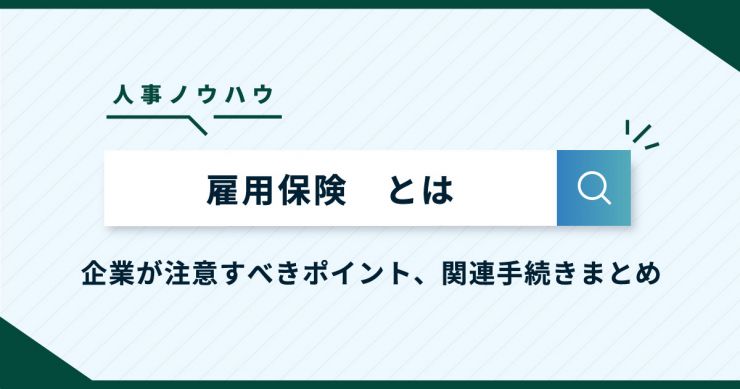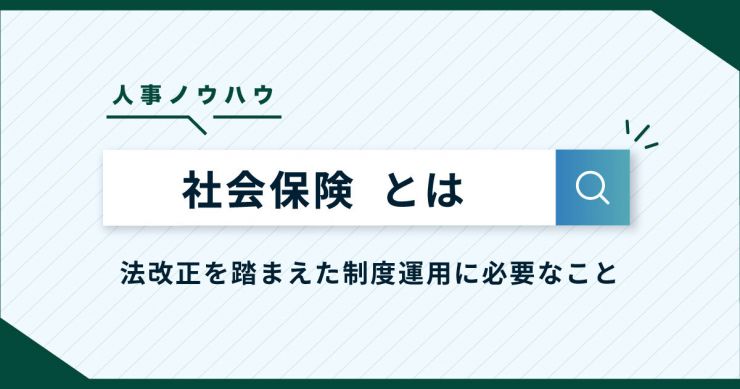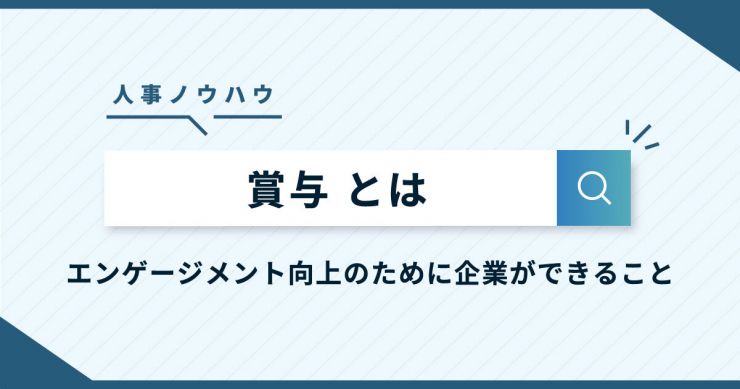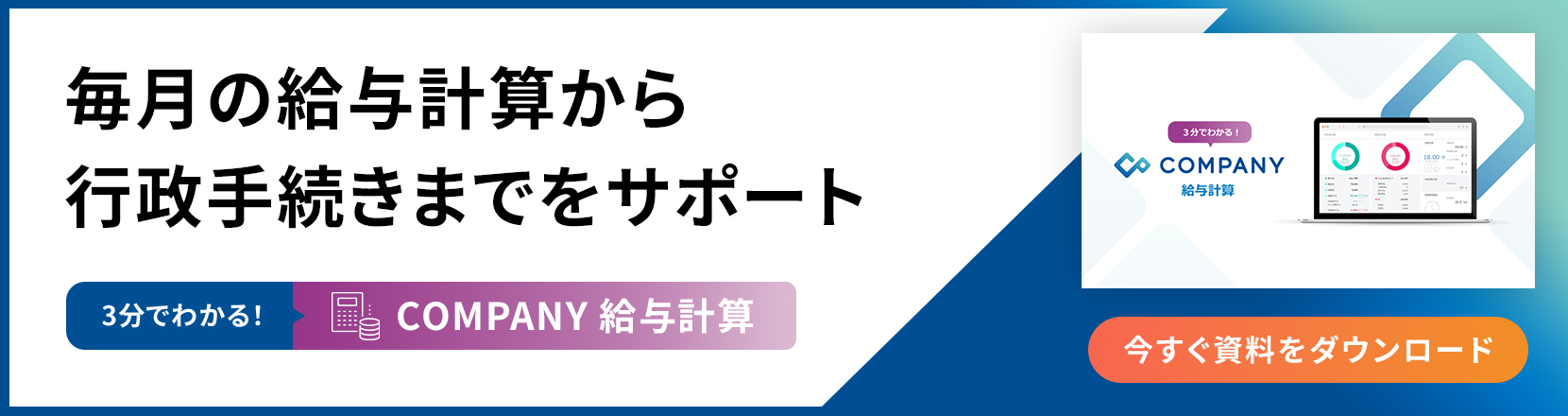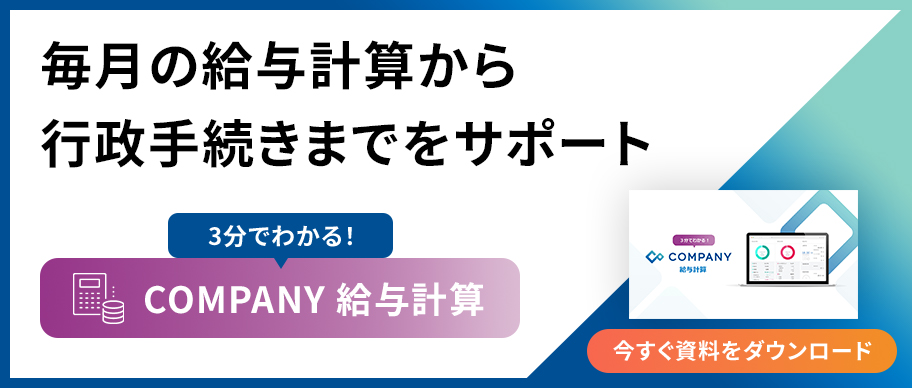雇用保険は労働者の生活や雇用の安定を保障する制度で、企業と従業員の両者によって保険料が納められています。
2022年度、2023年度は雇用保険料率の引き上げが続き、2024年度は据え置きとなりました。しかし、2025年には引き下げが検討されています。料率の改定に際して、企業はどのような対応が求められるのでしょうか。
本記事では、雇用保険の概要や保険料の計算方法、注意点などを解説します。制度の内容を正しく理解し、適切な対応を目指しましょう。
1分サマリ
-
・雇用保険料は事業主と従業員で負担し、従業員の給与、賞与から差し引かれる
-
・2025年度の雇用保険料は1.45%、2024年度から0.1%の引き下げが検討されている
-
・雇用保険料は毎年度6月1日から7月10日に概算保険料と確定保険料を納付する
-
・従業員を採用したり、従業員が離職した場合には書類提出が必要
目次
ー雇用保険とは
ー2024年度・2025年度の雇用保険料率
ー企業が負担する雇用保険料の計算方法
ー雇用保険料を計算する際の注意点
ー雇用保険の納付
ー雇用保険の加入要件
ー雇用保険に関連する手続き
雇用保険とは
雇用保険は社会保険の1つで、労働者の生活や雇用の安定を保障する制度です。労働者が失業して再就職を目指す際に、必要な給付や支援を受けられるよう、雇用保険料を積み立てています。
保険料の支払者は事業主と従業員の両方です。従業員の負担分は、給与や賞与から差し引かれます。
事業規模によらず、原則的に労働時間が週20時間以上で雇用の見込みが31日以上の労働者を対象とします。
2024年度・2025年度の雇用保険料率
雇用保険料率については、加入者からの収入と失業者への基本(失業)手当、雇用調整助成金の支給といった支出の状況に応じて、財政状況を考慮しながら毎年見直しが行われます。
新型コロナウイルス感染症拡大による雇用調整助成金の給付増加により、2022年度、2023年度と引き上げが続いてきました。2024年度は据え置きになりましたが、2025年度は引き下げが検討されています。
本章では2024年度と2025年度の雇用保険料率について解説します。
2024年4月1日~2025年3月31日の雇用保険料率
一般事業の雇用保険料率は1.55%です。
2023年度から変更がありませんでした。
▼2024年4月1日~2025年3月31日の雇用保険料率
| ①労働者負担 |
②事業主負担 |
①+②雇用保険料率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
⑴失業等給付 |
⑵雇用保険二事業の保険料率 | ⑴+⑵ | |||
| 一般の事業 | 0.6% | 0.6% | 0.35% | 0.95% | 1.55% |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 0.7% | 0.7% | 0.35% | 1.05% | 1.75% |
| 建設の事業 | 0.7% | 0.7% | 0.45% | 1.15% | 1.85% |
https://www.mhlw.go.jp/content/001211914.pdf
2025年4月1日からの雇用保険料率
2024年12月23日に開催された第201回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会で、一般事業の雇用保険料率を1.45%に引き下げる案が出されました。
現在、労使折半で負担している失業等給付の保険料率を0.1%引き下げることが検討されているため、労働者負担分が0.55%、事業主負担分は0.9%になると予想されます。
4月の給与計算では、新しい雇用保険料率で保険料を計算する必要があります。上記はまだ検討段階であるため、例年2月に厚生労働省から公表される新年度の雇用保険料率を確認しましょう。
参考:厚生労働省「財政運営について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001359918.pdf
企業が負担する雇用保険料の計算方法
雇用保険料の計算式は、「賃金額(総支給額)×雇用保険料率」です。企業が負担する保険料の計算手順は、大きく2つのステップに分けられます。
STEP①:賃金額(総支給額)を算出する
STEP②:事業ごとの雇用保険料率(事業主負担)をかける
本章では、雇用保険料の計算手順を詳しく解説します。
雇用保険料の計算手順
STEP①:賃金額(総支給額)を算出する
はじめに、従業員に対する支給額のうち、雇用保険料の計算において賃金額に該当する費目を確認しましょう。
基本的に、通常の業務に紐づいて安定的に支給される科目は賃金額に算入します。対して、休業補償や傷病手当、退職金等、特別な事情に基づいて発生する一時的な支給額は賃金とみなされません。
以下の表は、雇用保険料の計算において、賃金額に含む支給科目・賃金額に含まない支給科目の例を一覧にしたものです。
| 賃金額に含む | 賃金額に含まない |
|---|---|
| ・基本給、固定給等基本賃金 ・固定残業手当 ・超過勤務手当、深夜手当、休日出勤手当等 ・扶養手当、子ども手当、家族手当等 ・宿、日直手当 ・役職手当、管理職手当等 ・住宅手当、転勤手当、地域手当、単身赴任手当 ・資格手当、特殊作業手当、技能手当、教育手当 ・奨励手当 ・調整手当 ・賞与 ・通勤手当、定期券、回数券等 ・休業手当 ・創立記念日等の祝金 等 |
・役員報酬 ・休業補償費 ・退職金 ・結婚祝金、死亡弔慰金 ・災害見舞金、傷病手当金 ・年功慰労金 ・出張旅費、宿泊費等 ・会社全額負担の生命保険掛金 ・財形貯蓄のため事業主が負担する奨励金 等 |
ここから、雇用保険料の計算対象となる賃金額を算出します。
参考:厚生労働省「雇用保険料の対象となる賃金」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/dl/koyou-07.pdf
参考:厚生労働省 愛媛労働局「労働保険料の算定基礎となる賃金早見表(例示)」
https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/tetsuzuki/2030106.html
STEP②:事業ごとの雇用保険料率(事業主負担)をかける
求めた賃金額に、雇用保険料率をかけて保険料を算出します。企業が負担する雇用保険料を算出する場合は、事業主負担の雇用保険料率を使用します。
また、保険料率は事業によって異なるため、自社がどの事業に該当するかあらかじめ確認しておきましょう。農林水産業、清酒製造業、建築業を除く多くの企業は、一般の事業に当てはまります。
2025年1月現在の雇用保険料率は、以下の表から確認できます。
▼2024年4月1日~2025年3月31日の雇用保険料率
| ①労働者負担 |
②事業主負担 |
①+②雇用保険料率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
⑴失業等給付・育児休業給付の保険料率 |
⑵雇用保険二事業の保険料率 | ⑴+⑵ | |||
| 一般の事業 | 0.6% | 0.6% | 0.35% | 0.95% | 1.55% |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 0.7% | 0.7% | 0.35% | 1.05% | 1.75% |
| 建設の事業 | 0.7% | 0.7% | 0.45% | 1.15% | 1.85% |
参考:厚生労働省「令和6年度雇用保険料率のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/001211914.pdf
雇用保険料(事業主負担分)の計算例
以下は、企業が負担する雇用保険料の算出例です。
ここでは、2024年12月において、建設業で働くAさんの雇用保険料(事業主負担分)を例に考えます。
STEP①:賃金額(総支給額)を算出する
2024年12月において、Aさんに支給された費目は以下の通りです。
- ・基本給:20万円(★)
- ・固定残業代:5万円(★)
- ・通勤手当:2万円(★)
- ・在宅手当:3万円(★)
- ・傷病手当金:10万円
- ・出張費:3万円
-
以上のうち、賃金額(総支給額)に含まれる費目の合計を求めます。ここでは、★のついたものが賃金の対象です。
賃金額(総支給額)
=基本給〈20万円〉+固定残業代〈5万円〉+通勤手当〈2万円〉+在宅手当〈3万円〉
=30万円
-
STEP②:事業ごとの保険料率をかける
2024年12月時点で、建設業に勤めるAさんの雇用保険料率(事業主負担)は0.95%です。先に求めた賃金額(総支給額)にこれを乗じて、企業が負担する保険料を算出します。
雇用保険料(事業主負担)
=賃金額(総支給額)〈30万円〉×雇用保険料率(事業主負担)〈0.95%〉
=2,850円
-
雇用保険料を計算する際の注意点
本章では、雇用保険料を計算する際に注意すべき点を3つ紹介します。
-
1.賞与も賃金に含む
STEP①:賃金額(総支給額)を算出する で紹介した表の通り、雇用保険料算出の際には、賞与も賃金に含まれます。
ただし、労働の対価として通常支給される賞与とは別の「恩恵として支給される一時的な賞与」は適用外です。たとえば、金一封や大入り袋等は雇用保険料の計算に含まれません。
雇用保険料の計算時は、賞与の算入範囲を確認するようにしましょう。
2.端数処理は規定通りに実施する
雇用保険料を算出した結果1円未満の端数が発生した場合は、既定の方法で処理します。端数の処理方法は、厚生労働省により以下のように定められています。
⑴労働者負担分を賃金から源泉控除する場合
ー負担額の端数が50銭以下なら切り捨て、50銭1厘以上なら切り上げ
⑵労働者負担分を被保険者自身が事業主に現金で支払う場合
ー負担額の端数が50銭未満なら切り捨て、50銭以上なら切り上げ
例外として、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合、それに従って雇用保険料を計算することもできます。
参考:厚生労働省「雇用保険被保険者からの雇用保険料の控除方法」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/dl/keizoku-21.pdf
3.徴収は正しいタイミングで実施する
新規雇用者や労働時間を変更し、新たに雇用保険の対象となる従業員がいる場合、雇用保険料を徴収するタイミングに注意する必要があります。
給与形態にもよりますが、基本的には毎月給料を支給するたび、保険料を徴収するのが適切です。つまり、月末締め翌月25日に給与を支払う企業の場合、給与支払日の25日に給与計算対象期間の雇用保険料が徴収されます。
たとえば3月入社の従業員については、3月の賃金から計算された雇用保険料を、4月25日の給料支給時に源泉徴収します。
雇用保険の納付
雇用保険料の計算期間は毎年4月1日から翌年3月31日の1年間です。事業主は6月1日から7月10日の間に保険料の申告と納付をしますが、このときは概算保険料にて申告・納付を行います。その後確定申告をしたうえで、翌年の同じ時期に確定保険料との差額を納付し清算します。この手続きが雇用保険の「年度更新」です。
申告期限に申告と納付が間に合わなかった場合は、保険料が賃金・料率に関係なく決まり、保険料に10%の追徴金が課せられます。保険料が高額になる場合は、納付期限の7月10日以降3回に分割して納付することが可能です。
概算保険料とは
概算保険料は、年度当初に前もって納付する、年間雇用保険料の見込額です。賃金総額の見込額は前年度の賃金総額を参考に求めます。
確定保険料とは
確定保険料は、ある年度に支払った賃金から算出される、実際に発生した雇用保険料です。翌年度当初に確定保険料を申告し、あらかじめ納付した概算保険料との差額を納付することで精算します。
年度末または退職に伴う保険の消滅日までに、労働者へ支給した年間賃金総額に雇用保険料率を乗じて算出します。概算保険料より確定保険料の額が大きかった場合は追納が必要ですが、次の概算保険料に充当可能です。反対に確定保険料の額が少なかった場合は、過徴収分の還付を受けられます。
納付方法
6月1日から7月10日の間で「労働保険概算・確定保険申告書」に記入し、雇用保険料を申告・納付します。これらの年度更新の手続きは管轄の労働局や労働基準監督署、日本銀行で行うことができ、e-Govによる電子手続きも可能です。
労働局や労働基準監督署が抜き打ちで調査するため、過去の申告納付額が過少であれば差額分に加え追徴金まで徴収されることに注意しましょう。
雇用保険の加入要件
以下4つの要件に該当する場合、労働者は雇用保険に加入する義務があります。
| 要件 | 注意点 |
|---|---|
| ①適用事業所に雇用されている | 1人でも従業員を抱える事業所であれば、事業主や従業員の意志とは無関係に雇用保険への加入が必要 |
| ②31日以上の雇用は見込まれる | 正規雇用として雇用契約期間に定めがない場合や、更新規定はなくても過去31日以上の雇用実績がある場合にも適用される |
| ③週の所定労働時間が20時間以上 | 時間外労働のために実労働時間が週20時間を超過しても、雇用契約における所定労働時間が週20時間に満たない場合、雇用保険の加入は不要 |
| ④学生ではない | 例外として、以下に該当する学生は雇用保険が適用される ・卒業後も同一の企業での勤務が予定される ・休学中である(休学証明書が必要) ・事業主の指示や承認を得たうえで大学院に通っている ・定時制の学生である |
また、短期労働者や高齢の労働者に対しては、以下の要件も加わります。
日雇い労働者
日雇い労働者については、以下のいずれかに該当する場合、労働者自身が職業安定所にて加入手続きを行うことで「日雇労働被保険者」として雇用保険の適用を受けられます。
- ・適用区域内で適用事業所に雇用される者
- ・適用区域外に住み、適用区域内の適用事業所に雇用される者
- ・上の2者以外で職業安定所から認可を受けた者
短期・季節労働者
短期・季節労働者(*)は「短期雇用特例被保険者」に区分されます。季節労働者等、短期雇用が前提の労働者を対象とした雇用保険の加入条件は以下の通りです。
- ・短期的、季節的に雇用される仕事への従事が常態化している
- ・4か月~1年の雇用契約を結んでいる
- ・週30時間以上の所定労働時間が設けられる
短期・季節労働者であっても、1年以上継続雇用する場合は一般被保険者と同様の扱いです。
(*)季節労働者とは、海やスキー場、一部の農地等特定の季節や気象下に限定して雇われる労働者です。
65歳以上の労働者
2020年4月1日以降、一定の条件を満たした65歳以上の高齢労働者には雇用保険加入が義務付けられています。このような労働者は「高年齢被保険者」に分類され、以下の加入要件を満たした場合、雇用保険への加入が必須です。
- ・週20時間以上の所定労働時間が設けられる
- ・31日以上の雇用が見込まれる
なお、65歳以上で上記の要件を満たした労働者が雇用された場合、雇用から翌月10日までに職業安定所に「被保険者資格取得届」を提出する必要があります。
雇用保険に関連する手続き
前述の通り、労働者が一定の要件を満たす場合、企業は従業員を雇用保険に加入させることが義務付けられています。本章では、雇用保険に関連して企業が行う手続きについて解説します。
従業員を雇用する際の手続き
従業員を雇い入れた時点で、事業主は「雇用保険適用事務所」として管轄の職業安定所に届け出る必要があります。提出書類は以下の2種類です。
| 提出書類 | 提出方法 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 雇用保険適用事業所設置届 | 窓口にて直接提出 | 雇用翌日から10日以内 |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | 窓口、郵送、電子申請(e-Gov) | 雇用した翌月の10日まで |
なお、雇用保険被保険者資格取得届は新規で従業員を雇用する都度、職業安定所へ提出する必要があります。
雇用保険被保険者資格取得届が提出されると、後述の「雇用保険資格取得等確認通知書」と「雇用保険被保険者証」が交付されます。これらの書類は従業員が雇用保険に入っていることを証明する重要なものであるため、必ず従業員本人に渡すようにしましょう。
雇用保険適用事業所設置届の提出方法
雇用保険適用事業所設置届を提出する際の主な申請事項は以下の通りです。
- ・法人番号
- ・事業所の名称(社名省略は不可、個人事業主は氏名か屋号)
- ・適用事業所となった年月日(最初の従業員を雇用した日付)
- ・労働保険番号(労働保険関係成立届を提出した時に割り振られる番号)
- ・事業概要(具体的な事業内容)
- ・1日の平均従業員数(年間延べ労働者数 ÷ 年間所定労働日数)
- ・雇用保険被保険者数(一般・日雇い)
- ・賃金締切日(給与の計算期間と支払日)
労働基準監督署の受付印が付いた「労災保険の保険関係成立届」を同時に提出する必要があります。加えて会社の謄本、被保険者証、出勤簿、賃金台帳や労働者名簿等の各種証明書の用意も必要です。
雇用保険被保険者資格取得届とは
上述の通り、雇用保険被保険者資格取得届が提出されると、被保険者に対して以下2種類の書類が交付されます。
- ・雇用保険資格取得等確認通知書
- ・雇用保険被保険者証
「雇用保険資格取得等確認通知書」は、被保険者となった年月日や被保険者番号や、雇用保険加入の有無を確認できます。また、雇用保険被保険者証は転職時に転職先企業への提出が求められるため、加入者側で大切に保管するように周知しましょう。
従業員が離職した際の手続き
従業員が退職すると雇用保険の対象から外れます。従業員の離職時は、事業主による雇用保険消滅の手続きが必要です。具体的には、事務所側で管轄の職業安定所に以下2種類の書類を提出します。
| 提出書類 | 提出方法 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 雇用保険被保険者資格喪失届 | 窓口、郵送、電子申請(e-Gov) | 離職翌日から10日以内 |
| 雇用保険被保険者離職証明書 (離職証明書) |
離職証明書が受理されると、離職票が発行されます。この離職票は失業給付金の受給に必要であるため、必ず退職者に郵送されなくてはなりません。退職者の次の一歩を応援するためにも、事務所側は離職証明書の提出が遅れないよう注意しましょう。
雇用保険被保険者資格喪失届とは
雇用保険被保険者喪失届は、従業員の離職につき雇用保険の適用から外れることを申告するための書類で、先述の雇用保険被保険者資格取得届とは反対の関係にあります。
離職のケースとして、退職や死亡、転籍を伴う出向等で従業員が会社を去った場合が挙げられます。また、従業員が役員となった場合も雇用保険被保険者喪失届を職業安定所に提出する義務があるため注意しましょう。
雇用保険被保険者離職証明書とは
雇用保険被保険者離職証明書(離職証明書)とは、従業員が退職後に離職票を請求するために必要な書類です。離職票がないと失業給付の受給手続きができないため、退職者が交付を求めた場合は必ず郵送しましょう。
また、59歳以上の従業員が退職する際には、従業員が求めなくても離職証明書の提出が必要です。これは離職証明書の一部が、60~65歳までが受けられる「高年齢雇用継続給付」の申請に必要であるためです。
雇用保険料の計算方法を理解し正しい運用を
本記事では、雇用保険の概要や保険料の計算方法、注意点等を解説しました。
雇用保険は事業者が従業員を守る目的に加え、日本の労働者が安全に働ける環境を担保する意味でも重要な制度です。それだけに、雇用保険料の額が誤っていた場合は従業員からの不信感が高まり、労使関係の悪化を招くことも考えられます。
雇用保険料率は加入者からの収入と給付に要する支出の状況に応じて、毎年見直されるので、企業は常にその年度の料率を把握したうえで、プロへの計算代行やツールを導入する等して雇用保険料を正しく算定・運用できるようにしましょう。