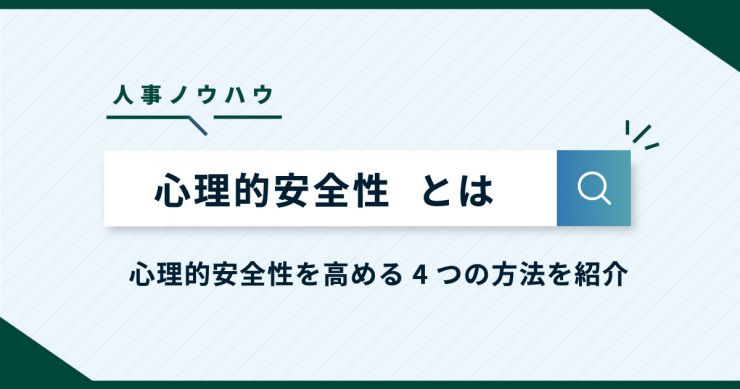組織開発で押さえておきたいキーワードの一つが「心理的安全性」です。心理的安全性が高い組織では、メンバーが能力を発揮しやすく生産性の向上が期待できるため、多くの企業が心理的安全性を向上させる取り組みを実施しています。
本記事では、心理的安全性の意味や高めるメリットや効果的な人事施策を紹介します。
組織開発で重視される「心理的安全性」とは
近年、組織開発やチームビルディングにおいて「心理的安全性」を高めることが重要視されています。心理的安全性は心理学用語「psychological safety(サイコロジカル・セーフティ)」の和訳で、ハーバード・ビジネス・スクールの組織行動学者であるエイミー C. エドモンドソン教授が1999年に提唱しました。
まずは、心理的安全性の意味や概念について見ていきましょう。
組織における心理的安全性
心理的安全性とは、組織の中で自身の考えや気持ちを誰に対してでも安心して発言できる状態を指します。
これを職場に当てはめると、自らの意見や疑問に感じていることを述べたとしても、拒絶や非難をされる心配がなく「このチームなら率直に発言しても大丈夫だ」という認識がメンバー間で共有された状態です。
たとえば、職場の上司や自分より長い経験を持つ人に対してでも、意見やアイデアを述べることできるのは、心理的安全性が高い状態です。
逆に「これは間違っているのでは?」「こう変えたほうがよいのではないか」と思っても、相手の地位や経験を気にして言えない場合は「心理的安全性」が低い状態といえます。
このような心理的安全性が低い職場では「提案や意見を述べても意味がない」「発言や行動をする必要はない」という雰囲気になりやすく、従業員のモチベーションやパフォーマンスの低下に繋がりかねません。
また、業務の円滑化に欠かせない「報告・連絡・相談」などの社内コミュニケーションが減り、ミスやトラブルに迅速に対応しづらくなることも懸念されます。
心理的安全性が高い組織のメリット
心理的安全性が高い状態は、組織に様々なメリットをもたらします。本章では4つのメリットを紹介します。
メリット1.パフォーマンスが向上する
心理的安全性が担保された職場では、上司や同僚の顔色や人間関係を気にする必要がなくなるため、仕事に集中して取り組めるようになります。
「自分の発言・行動が尊重されている」という安心感から仕事に対するモチベーションが向上し、生産性や成果の向上に繋がります。
メリット2.コミュニケーション・情報共有が活発になる
誰もが気兼ねなく発言できる職場では、メンバー間のコミュニケーションが活性化します。目標達成や課題解決に向けた建設的な議論が増えるだけではなく、知識やノウハウの共有も積極的に行われるようになるため、チームのレベルアップに繋がります。
メンバー間の情報共有がスムーズになることで、トラブルに発展しそうな問題にいち早く気づき、対処することも可能です。
メリット3.イノベーションが生まれやすくなる
職場の心理的安全性が保たれていると、多種多様な意見やアイデアが集まりやすくなります。現状維持をよしとせず、新たな視点のアイデアやチャレンジが受け入れられる職場環境であるため、新規事業や業務改善に繋がるイノベーションの創出が期待できます。
メリット4.従業員のエンゲージメント・定着率が向上する
心理的安全性が高い職場では、一人ひとりが自分らしくいることができ、能力を存分に発揮できます。伸び伸びと仕事に取り組めるため、組織に対するメンバーのエンゲージメント(愛着や信頼感)が高まり、定着率の向上に繋がります。
人手不足が深刻化している昨今、従業員のエンゲージメントを高めて離職を防ぐことは重要です。
【人事・マネージャー向け】心理的安全性を高める4つの方法
自社の心理的安全性を高めるために、人事部門として何をすればよいでしょうか。ここでは、心理的安全性の向上に役立つ人事施策を4つ紹介します。
1on1ミーティングやメンター制度を導入する
従業員一人ひとりが安心して自分の意見を表明できる環境づくりの一環として、1on1ミーティングやメンター制度を導入することは有効です。
上司と部下が1対1で行う1on1ミーティングでは、業務以外のことも含めた部下の悩みや将来のビジョン等を共有します。上司と部下のコミュニケーションの機会が増えることで、相互理解が深まり、信頼関係を構築しやすくなります。
メンター制度は、先輩社員が後輩社員や新入社員の相談役(メンター)となり、仕事や人間関係、キャリア形成等についてアドバイスを行う制度です。
一般的に、業務上の上下関係・利害関係のない先輩社員がメンターに任命されるため、上司に言いづらいような悩みも気軽に相談しやすく、メンタル不調や早期離職を防ぐ効果が期待できます。
上司や先輩社員との定期的な対話を通じて「自分の状況を理解してもらえている」「意見を尊重してもらえる」という安心感が高まり、心理的安全性を醸成できるでしょう。
OKRを設定する
OKR(Objectives and Key Results)は、組織全体の目標を基にチームの目標を設定し、さらに各メンバーの目標に落とし込んでいく目標管理の手法です。
OKRでは、組織全体の目標とメンバー一人ひとりの目標がリンクしているため、自社における自分の役割や業務の優先順位が明確にわかります。また、自分の活動が組織全体の成果に直結していると実感でき、モチベーションや主体性の向上に繋がります。
チームや個人の目標が明確になることで、目標達成に向けてメンバー間の協力体制を築きやすくなり、心理的安全性の向上に寄与します。
人事評価制度を見直す
心理的安全性が損なわれる要因の一つは、従業員が人事評価制度に不満を抱えているケースです。
たとえば、人事評価の基準が不明瞭で上司の一存で評価が決まることが多い場合、部下は上司の顔色をうかがって進言や提案を控えてしまいます。評価に不公平さを感じたメンバーが、同僚の足を引っ張るような行動を取る可能性もあります。
従業員の自発的な行動や新たなチャレンジを促進し、より健全な職場環境を構築するためには、公正で透明性の高い人事評価制度が不可欠です。
現行制度に課題を感じる場合は、「自分の活動が正当に評価されている」「評価プロセスがわかりやすい」と従業員が思えるような評価制度に改善しましょう。
管理職・リーダー層向けの研修を実施する
管理職やリーダー層の言動は、職場の心理的安全性に大きな影響を与えます。
チームのマネジメントを担う人が心理的安全性を意識した発言や行動をすることで、メンバー一人ひとりが伸び伸びと働ける職場環境を構築しやすくなります。そのため、管理職やリーダー層を対象に「心理的安全性」をテーマにしたマネジメント研修を実施するのも一案です。
心理的安全性を高めるコミュニケーションの仕方や心構え等を体系的・実践的に学ぶことで、チーム力の向上に繋がるマネジメント力が身に付きます。
心理的安全性を意識した組織づくりを
心理的安全性が高い職場は、従業員が存分に能力を発揮できる環境であるため、モチベーションやエンゲージメントの向上に繋がります。メンバー間のコミュニケーションや新たなアイデアが増えることで、生産性が高まり、イノベーションも生まれやすくなります。
心理的安全性は一朝一夕で高められるものではないため、人事部門が中心となって組織全体で向上策を推進することが重要です。目標管理手法や人事評価制度を見直す、マネジメント研修を強化する等、心理的安全性の向上に役立つ人事施策は様々です。
まずは、心理的安全性とは何かを理解したうえで、自社の課題に合った向上策を取り入れましょう。