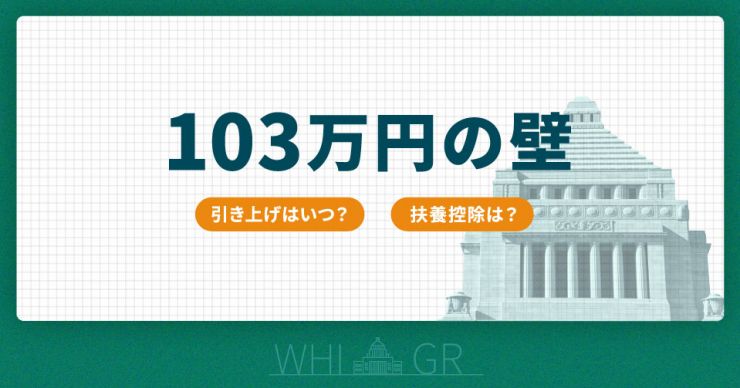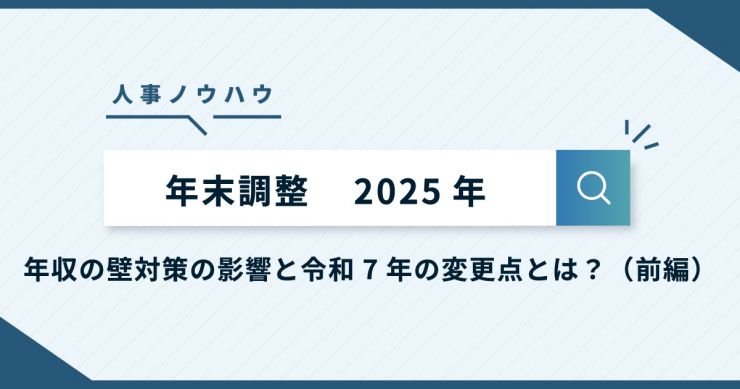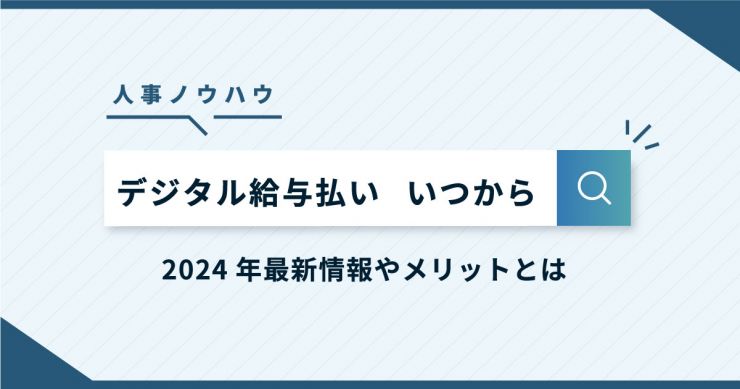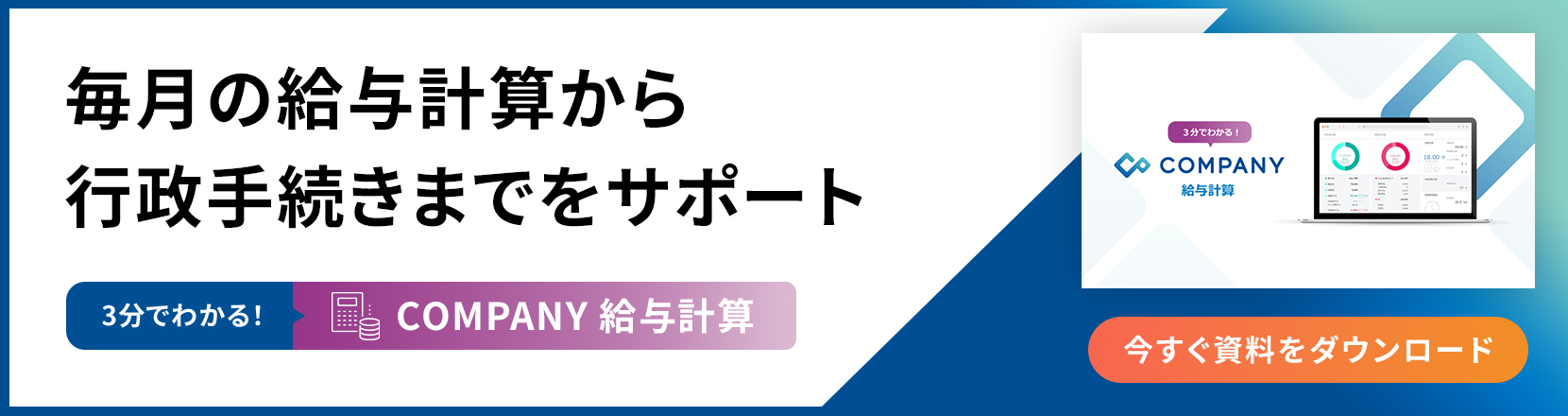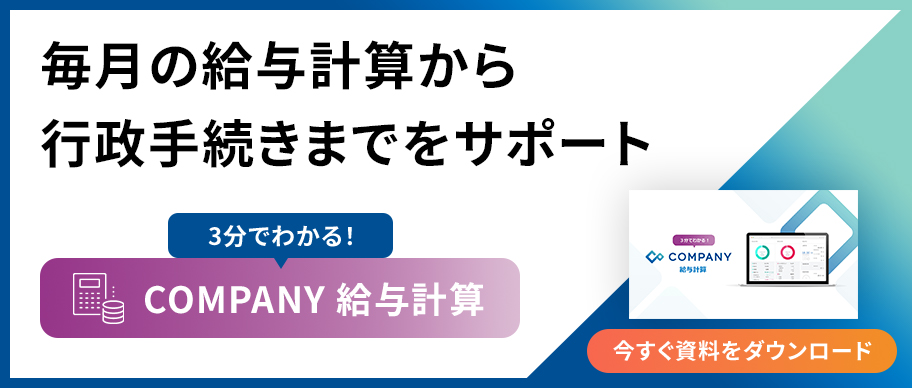給与所得とは、勤務先から受け取る給与、賞与等から経費を除いた部分のことです。今回は、給与所得の概要や給与収入との違い、給与所得に関連する控除についてご紹介します。経理・労務担当にかかわらず事業を行う人にとっては必要な基礎知識であるため、しっかりと押さえておきましょう。
目次
給与所得とは
給与所得とは、労働者に支払われた給与、賞与等から経費とみなされる給与所得控除額を差し引いた金額です。給与、賞与すべてが給与所得になるわけではない点に注意しましょう。
一般的に、勤務先から労働者に支払われるお金は「給与収入」「給与所得」等と表現されます。これらの言葉は同じものを指すと考える人が多いですが、実際の意味は異なります。
給与所得と給与収入の違い
給与収入と給与所得は混同されやすいですが、両者には明確な違いがあります。具体的には以下の通りです。
・給与収入: 勤務先から受け取った給与、賞与等の合計金額。基本給や賞与、残業代を含む。
・給与所得: 年末調整や確定申告で年間の給与所得額を確定するために、1年間で受け取った給与収入の合計額から給与所得控除額を差し引いた金額
なお給与所得には、通常の俸給・給料・賃金・諸手当・賞与だけでなく、現物給与も含まれます。現物給与の一例としては、物品の譲渡・福利厚生施設の無償提供等です。
参考:国税庁「No.2508 給与所得となるもの」
給与所得控除とは(令和7年税制改正における変更点)
給与所得は、給与等の収入金額から経費とみなされる一定金額を控除して算出します。この控除を給与所得控除といい、1年間の給与収入に応じて金額が変わります。
給与所得控除として引かれた金額は、所得税の課税対象に含まれません。
給与所得控除額の計算式は国税庁により定められており、以下の表に基づいて算出されます。
なお給与所得控除については、2025年(令和7年)の年末調整から、年収の壁対策として55万円の最低保障額が65万円に引き上げられます。
| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 改正後(令和7年) | 改正前 | |
| 162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5,000円超 180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超 190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
| 360万円超 660万円以下 | 収入×20%+44万円 | |
| 660万円超 850万円以下 | 収入×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) | |
出典:国税庁「No.1410 給与所得控除」
出典:国税庁「昨年と比べて変わった点(基礎控除の見直し等)」
給与所得の計算例
給与所得は、国税庁によって定められた計算式を利用し、年間の給与収入から給与所得控除額を引いて計算します。年収が500万円の方を例に、まずは給与所得控除額を算出してみましょう。
500万円×20%+44万円=144万円
上記の計算から、給与所得控除額は144万円となります。次に、年間の給与収入から給与所得控除を差し引いて給与所得額を出します。
500万円(年間の給与収入額)-144万円(給与所得控除額)=356万円
このように、年収が500万円だった場合の給与所得は356万円であることがわかります。
参考:国税庁「No.1410 給与所得控除」
パート・アルバイトはいくらまで稼げる?令和7年、非課税ラインが「160万円」に
2025年(令和7年)の税制改正により、給与所得控除と基礎控除が引き上げられた結果、年収の非課税ライン(所得税がかからない年収の上限)が大きく変わりました。とくに、年収が変動しやすいパート・アルバイト労働者にとっては「どのくらいの年収までなら所得税を負担せずに稼げるか」が気になるところでしょう。
これまで「103万円の壁」と言われた非課税ラインは、給与所得控除(改正前55万円)と基礎控除(改正前48万円)の合計103万円から算出されていました。
2025年分以降、この年収の壁は以下の通り変更されます。
・給与所得控除: 最低保障額が65万円に引き上げ
・基礎控除: 控除最大額が95万円に引き上げ
この改正により、給与収入が低い層では、給与所得控除と基礎控除の合計額が最大で160万円(給与所得控除65万円+基礎控除95万円)となり、所得税がかからない年収のラインは、実質的に160万円まで引き上げられました。
参考:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
所得控除とは
所得控除とは、所得税額の算出にあたり、給与所得額から差し引かれる控除のことです。
先述の給与所得控除と似た名称ですが、中身はまったく異なります。
・給与所得控除:給与収入額から、収入に応じて算出された額が差し引かれる控除
・所得控除:条件を満たす人が申告した場合に、給与所得額から差し引かれる控除
所得控除の例
給与所得控除には複数の種類があり、先述の「基礎控除」は所得控除に含まれます。下の表では、さまざまな所得控除のうち主なものを紹介します。これらの所得控除は、年末調整で自らが対象者であることを申告することによって受けられます。
| 基礎控除 | ・確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除 |
|---|---|
| 医療費控除 | ・病気や怪我で医療費が一定額を超えた場合に受けられる控除 ・治療費や特定の薬剤費、通院交通費等が対象 |
| 社会保険料控除 | ・社会保険料を支払った際に受けられる控除 ・国民健康保険・健康保険、国民年金・厚生年金保険、介護保険、雇用保険等が対象 |
| 生命保険料控除 | ・1年間の生命保険料の金額に応じて一定の金額を控除 ・一般的な生命保険、介護医療保険、個人年金保険が対象 |
| 地震保険料控除 | ・地震保険料や掛金の支払いに応じて、一定の金額を控除 ・控除額は、1年間の支払額が5万円以下であれば全額、5万円を超える場合は金額に限らず一律5万円 |
| 配偶者控除 | ・所得税法上の控除対象配偶者を有している場合に受けられる控除 ・控除額は、納税者の合計所得額・控除対象配偶者の年齢によって決まり、納税者の合計所得額が1,000万円を超える場合は配偶者控除の対象外 |
参考:国税庁「No.1100 所得控除のあらまし|国税庁」
これらの控除の対象には、生計を共にしている人も含まれています。
特定支出控除とは
給与所得の控除には、所得控除だけでなく特定支出控除というものも存在します。特定支出控除とは、給与所得者が転居や資格取得等、特定の支出をした場合に適用される控除です。
こちらの控除は、年末調整での申告はできません。対象となる支出が給与所得控除額の1/2にあたる金額を超えた場合、確定申告をすることで給与所得控除後の所得金額からさらに控除できます。
特定支出控除の対象となる支出は以下の通りです。
| 通勤費 | 通勤時に交通機関を利用した際の支出 |
|---|---|
| 転居費 | 会社の辞令で引っ越しをする際にかかる費用 |
| 研修費 | 業務に必要な知識・技術を習得するためにかかった、講習・研修の費用 |
| 資格取得費 | 業務に必要な資格を取得するためにかかった費用 |
| 帰宅旅費 | 単身赴任をしている従業員が自宅に帰宅する際にかかる費用 |
| 勤務必要経費 | 業務で必要と認められた経費(支出額の限度は65万円) |
資格取得費に関しては、結果的に資格を取得できなかった場合でも、要件を満たせば特定支出控除として認められます。勤務必要経費の一例としては、業務に関する図書の購入費用や、勤務中に着用する衣服の購入費用等が該当します。
なお、上記すべてにおいて支出を証明できることが必須です。要件は細かく定められているため、特定の支出に該当するかについては慎重に調べる必要があります。
参考:国税庁「No.1415 給与所得者の特定支出控除」「給与所得者の特定支出控除について」
所得金額調整控除とは
所得金額調整控除とは、子どもがいる方、本人や家族が障がい者である方、給与所得と年金所得の双方を有する方が対象の所得控除です。所得金額調整控除には、年末調整で申告するものと確定申告で申告するものがあります。
それぞれの所得金額調整控除は以下の計算式で算出されます。
①子どもがいる方・本人や家族が障がい者である方(*)
(給与等の収入金額−850万円)×10%
(*)厳密には「子ども・特別障害者等を有する者等」と呼ばれています。
②給与所得と年金所得の双方を有する方
(給与所得控除後の給与等の金額+公的年金等に係る雑所得の金額)-10万円
所得金額調整控除は、年収850万円を超える子育て世帯や介護世帯の負担軽減を目的とした措置です。所得税は給与所得に所得税率を乗じて算出されるため、控除制度を利用して所得金額を少なく調整すれば納付する税額を減らせます。
下記のいずれかが該当する場合は、上述の①を満たし、所得金額調整控除の対象となります。
・本人が障がいを有する
・23歳未満の扶養家族がいる
・扶養親族・同一生計配偶者に障がい者がいる
①の計算には、以下の点に注意しましょう。
・給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、1,000万円で固定して計算
・1円未満の端数を切り上げ
参考:国税庁「No.1411 所得金額調整控除」
所得税の計算方法
一定の給与収入を得ている場合は、所得税が課せられます。所得税は、給与所得から所得控除額を引いた金額に、所得税率をかけて計算します。
(給与所得ー所得控除)× 所得税率 = 納めるべき所得税
所得税率は、課税される所得の金額に応じて国が決めています。課税される所得金額とは、年間の給与所得から所得控除を差し引いた金額です。平成27年分以降の所得税の速算表は下記の通りです。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
算出された所得税額は1,000円未満で切り捨てます。たとえば給与所得が450万円、所得控除が190万円の場合は、所得税率が10%になり(*)、26万円と計算できます。
(450万円-190万円)×10%=26万円
(*)出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」
給与所得にかかわる届出
企業が給与所得の管理業務を行ううえでは、いくつかの届出が必要です。主に使用される書類は「給与所得者の基礎控除申告書」「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者異動届出書」の3種類です。
給与所得者の基礎控除申告書
給与所得者の基礎控除申告書とは、「納税者本人の生活に必要な部分には税金を課さない」という証明をする書類のことです。納税者本人の合計所得金額が2,500万円以下の場合に、記入が必要です。
給与所得者の基礎控除申告書では、配当所得・不動産所得・事業所得等の記入欄があります。該当する所得欄に、計算した金額を正確に記入しましょう。各所得計算方法には以下のようなものがあります。
| 所得の種類 | 計算方法 |
|---|---|
| 利子所得 | 収入金額-元本取得に要した負債の利子 |
| 配当所得 | 総収入金額-必要経費 |
| 事業所得 | 総収入金額-必要経費 |
| 給与所得 | 収入金額-給与所得控除額 |
| 雑所得・公的年金 | 収入金額-公的年金等控除額 |
上記の他にも申告すべき所得がいくつかあるため、従業員がなんらかの手段で収入を得ている場合は、該当する所得が何に当てはまるかを押さえておきましょう。
参考:国税庁「No.2011 課税される所得と非課税所得」
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは、配偶者や親族が扶養家族に該当する場合に、配偶者の所得控除を受けるために必要な書類のことです。それぞれの欄の書き方は以下の通りです。
| 記入欄 | 記入方法 |
|---|---|
| 所得税務署長等 | 給与支払者の所在地等を管轄する税務署・市区町村長の名称 |
| 給与の支払者の名称(氏名) | 企業名 |
| あなたの個人番号 | マイナンバーが記載された帳簿を添付する場合は記入不要 |
| 従たる給与についての扶養控除等申告書の提出 | 2か所以上から給与を受け取っている場合は「○」 |
| 老人扶養親族 / 特定扶養親族 | 該当する場合に「○」 |
| その年の所得の見積額 | 控除対象配偶者・控除対象扶養親族が得ている所得の見積額 |
| 6歳未満の扶養親族 | 該当する控除対象扶養者の情報 |
記入漏れがないよう、従業員に記入内容の確認を促しましょう。
出典:国税庁「各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)」
給与所得者の異動届出書
給与所得者異動届出書とは、退職・転勤・休職・死亡等を理由として、従業員(納税義務者)が給与の支払いを受けなくなった際に提出する書類です。住民税の特別徴収を止めるために、特別徴収義務者(給与支払者)が市町村に提出します。
ケースによって提出期限が異なるため、事前に確認の上、期限内に届け出ましょう。
給与所得について理解し、正確な税額計算を
給与所得は、勤務先から受け取る給与や賞与から給与所得控除額を差し引いた金額です。所得税を計算する際には、給与所得控除、所得控除、特別控除等いくつかの所得控除が適用されます。所得税額を算出するうえで、様々な控除についての知識を身に付けておくことは経理・労務・経営にかかわる方にとっては必須です。
給与所得や各種控除、控除の対象となる要件について理解し、正確に税額を計算できるようになりましょう。