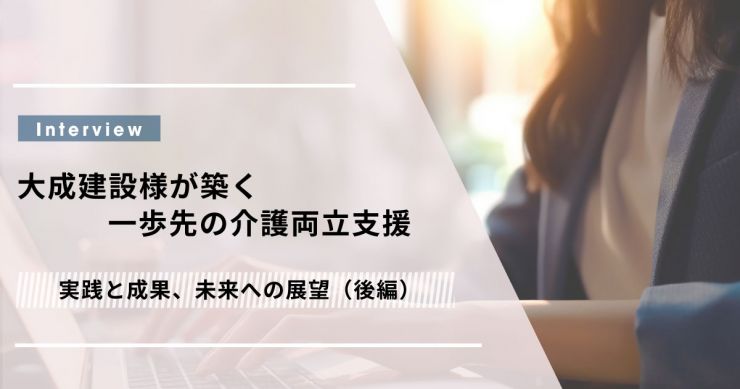2025年を迎え、団塊の世代がすべて75歳以上となったことから、高齢者の介護需要が急増すると想定されます。こうした中、家族の介護を理由に離職する「介護離職」への対応は、企業にとって喫緊の課題です。今後は、働きながら介護を担う“ビジネスケアラー”もさらに増える見込みであり、制度整備と職場環境づくりの両面で早急な対応が求められます。
大成建設株式会社(以下、大成建設)様は、2010年と早い時期から、介護と仕事の両立支援に取り組まれてきました。課題が顕在化する前に先手を打った同社の取り組みは、人材定着や組織力の強化にも繋がっています。
本対談では、管理本部 人事部 人財いきいき推進室 北迫 様にWHI総研角川・眞柴がインタビュー。大成建設様における制度設計の背景から現場での活用、社内文化の醸成、そして今後の展望までを伺いました。
後編となる本記事では、介護両立支援の現場での実践、制度の成果、そして未来を見据えた展望をお届けします。
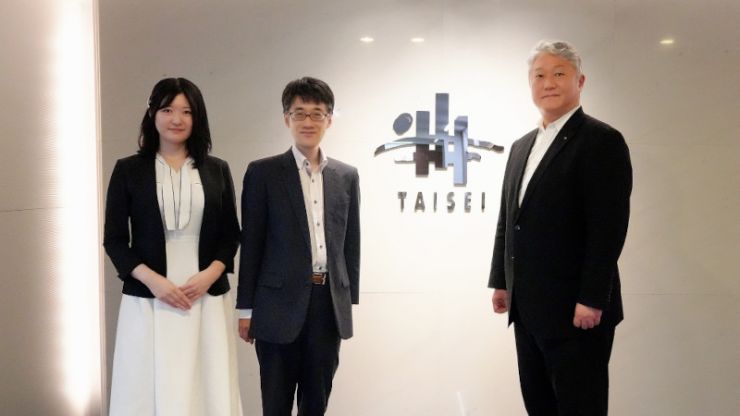
今回の対談者
北迫 泰行 様(写真右)
大成建設株式会社 管理本部 人事部人財いきいき推進室長
介護経験で得られるスキルの活用と可視化の可能性
Q5.介護経験で培われるマネジメント力と実務への活用について教えてください。
角川:
介護は、予期せぬ事態への対応力、時間管理、多職種や家族との調整力、困難に直面しても前向きに対処する力など、多くの実務的スキルを磨く機会になると考えています。貴社では、こうした介護経験で得られるスキルをどのように捉えていますか。
北迫様:
まさに介護は「マネジメント」そのものです。
初期対応として家族を病院に連れて行く場面から、家族間で「いつ・どうする・誰が担当する」といった意思決定や役割分担の調整に至るまで、プロジェクト管理と同様の能力が求められます。
こうした経験を通じて、限られた時間やリソースの中で最適な判断を下し、関係者の合意形成を図るといったマネジメント力・調整力が磨かれるものと認識しています。
角川:
そうしたスキルが実務に活かされた具体的な事例はありますか。
北迫様:
私自身も介護経験があるので、その観点からお話しすると、介護を通じて特に磨かれたのは、場所や時間に縛られず業務を進める対応力だと感じています。
急な事態でも、移動中にタブレットやスマートフォンで指示を出したり、音声でWeb会議に参加したりと、柔軟に業務を継続できるようになりました。これにより、チャットによる決裁や資料承認なども迅速に行えるようになりました。
また、私自身の経験に限らず、職場では介護経験が周囲の働き方にも影響を与えるケースがあります。
たとえば、介護経験のない上司が、介護を抱える従業員に「案件ごとに逐一承認をとるのではなく、自ら判断して後で報告すればよい」と決裁権を預けた事例が社内にもあります。信頼関係と柔軟な判断により、仕事のフローを変えて介護との両立を実現した好例です。
角川:
介護は配慮が必要な事情として語られることが多いですが、実際には高度なマネジメントスキルが身につく経験でもありますね。その経験やノウハウを組織全体で共有できれば、個人の成長だけでなく組織力の向上にも繋がりますね。
介護離職のリスクをより早期に可視化・把握するための施策
Q6.介護離職のリスクを早期に可視化・把握するための取り組みについて教えてください。
角川:
貴社では、介護離職予備軍を事前にリスト化するというよりも、従業員や管理職からの働きかけを通じて個々の状況を把握していると伺っています。今後、介護離職のリスクをより早期に可視化・把握するための施策は検討されていますか。
北迫様:
介護離職予備軍を可視化するためのリスク分析手法はまだ導入できていませんが、可視化できればより具体的な対策を講じられるため、今後はぜひ取り組みたいと考えています。
眞柴:
休暇や休業を取るまでには至らないが、実は両立に苦しんでいる、あるいは「今は大丈夫」として声を上げないケースの把握は難しい部分もありますよね。
当社、WHIでは、毎月の健康チェックで「イライラする」「眠れない」といった状態や労働・休息環境について回答し点数で自覚できるほか、「業務の完了見込みとその理由」を自由記述し、それを上司に開示するかも従業員自身が選択できる仕組みを導入しています。
管理部では、そのデータの変化と勤怠情報を突き合わせ、状況把握を試みていますが、運用には相応の労力もかかるので、試行錯誤しているところです。
北迫様:
上司に開示するかどうかを従業員が選べる、心理的安全性を保ったしくみは素晴らしいですね。
当社でもアンケートを実施していますが、質問数が多く従業員に負担をかけている面があります。そこで、年1回のストレスチェックに「介護をしていますか」といった質問を3〜4問追加し、自然な形で尋ねることで、実態を把握する工夫をしています。
こうして得られたデータは、厚生労働省のガイドラインでも重要性が示されている通り、経営層へ現状を伝えるための客観的な根拠になります。「リスク」という言葉は強い印象を与えますが、突発的に休む必要が出た際や日常生活に支援が必要になった際に、会社や同僚、部下が事前に状況を理解しておくことは極めて重要です。
私自身も、自分のスケジュール欄に「介護のため休み」と明記し、部下にも親の介護であることを伝えています。周囲にも認識してもらって、協力もお願いすることで、急な事態にも柔軟に対応できる環境をつくっています。
角川:
介護離職のリスク可視化は、制度面の整備や支援施策の充実と同じくらい、現場のマネジメントや組織文化に深く関わるテーマだと感じます。
単に予備軍を特定するだけでなく、従業員が安心して状況を共有できる心理的安全性を確保し、その情報をもとに早期の声かけや業務調整をしていくことが、結果的に離職防止や組織力の強化に繋がりますよね。可視化の手段と活用方法の両輪を整えることが、今後の重要な鍵になりそうです。
介護両立支援の成果と企業としてのゴールとは
Q7.介護両立支援は、人材定着やスキル活用、職場内の相互理解・支援体制強化を通じて、どのように生産性向上に貢献していますか。
北迫様:
当社の介護両立支援は、従業員の離職防止と人材定着に直接的な効果をもたらし、それが結果的に生産性の維持に繋がっています。たとえば、介護セミナー後のアンケートでは「会社の制度がなければ離職していた」という声が一定数寄せられており、制度のおかげで戦力の流出を防げていたことがわかります。
現在、なんらかの介護をしている従業員は約1,000名、さらに「今後5年以内に介護に直面する可能性がある」と回答した従業員は全体の22%に上ります。つまり、5年以内に約3割の従業員が介護に直面する可能性があるという状況です。こうした中で、介護離職を防ぎ、支援策を継続的に周知・活用してもらうことが、生産性低下を防ぐために不可欠だと考えています。
角川:
介護を担う従業員の割合や将来の見込みを踏まえると、制度の存在そのものが企業の持続的な成長を支える土台になっていると感じます。特に、離職を防ぎながら経験やスキルを社内に蓄積できる点は、組織の競争力維持にも直結しますね。
制度のアップデートについても、継続的に行われているのでしょうか。
北迫様:
はい。たとえば介護休暇の日数は、法定日数より少しずつ増やしてきました。これは従業員の平均取得日数などの実態調査を踏まえて見直した結果です。
今後は、介護休業による一時的な不在時に、その穴を埋める周囲の従業員への何らかのフォロー策も検討していきたいと考えています。これは男性の育児休業支援でも議論されているテーマですが、介護の場合はまだ明確な答えがなく、当社としても模索している段階です。
角川:
介護両立支援は、将来的な人材流出の抑制や経験・スキルの蓄積といった、経営的にも大きな意義を持つ取り組みだと改めて感じました。制度の存在が従業員の安心感を生みだし、その安心感が生産性と組織力の維持に繋がっているのですね。
今後の制度アップデートによって、より多様な状況に対応できる支援体制がいっそう充実していく様子を拝見できればと思います。

介護両立支援策を推進するために
Q8.経営層のコミットメントは介護両立支援やダイバーシティ推進の浸透にどのような影響を与えていますか。
北迫様:
経営層のコミットメントは極めて重要です。以前、約20ページの社内報のうち6ページを介護離職防止の特集に充て、社長自ら「介護離職対策は会社の責務です」と明言しました。
その直後から、「親が要支援1だが介護休暇は取れるか」といった具体的な相談が急増しました。トップが理解を示し、方針を明確に打ち出すことで、従業員は安心して声を上げられるようになります。
介護支援をこれから始める企業には、必ずトップがコミットすることを勧めています。「介護している従業員はいない」という経営層の方もいるかもしれませんが、実際は「言えないだけ」である場合がほとんどです。
従業員の実態を把握したうえで、「これだけ困っている従業員がいる」という事実を経営層に示すことが、理解と行動を促す最も効果的な方法だと考えています。
角川:
経営層からの力強いメッセージが、従業員の行動や意識をこれほど変えるのだと改めて感じます。声を上げられなかった人が安心して相談できるようになることは、制度の活用促進や離職防止にも直結しますね。
北迫様:
経営層の理解があることで、現場の管理職も柔軟な対応を取りやすくなります。実際に、介護を担う部下に対し、仕事のフローを見直し、決裁権限を委譲するなどの事例もあります。こうした動きは、組織全体の理解を広げ、生産性向上にも繋がると考えています。
大成建設様は、働き方改革を阻害する要因を先回りして解消するという発想のもと、2010年という早い段階から介護と仕事の両立支援に取り組まれてきました。
インタビューを通じて印象的だったのは、この取り組みが単なる制度対応にとどまらず、人材定着や組織力の向上といった経営的視点と結びつけられている点です。
また、介護は配慮すべき個別事情として語られがちですが、同社では「マネジメントそのもの」と捉え、突発的な対応や関係者との調整、役割分担の判断など、実務に直結するスキルの習得機会と捉えられている点も興味深く感じました。実際に、介護経験を通じて得たスキルが仕事に活かされているという具体的な事例も印象深いです。
制度・風土・データを有機的に結びつけながら、従業員一人ひとりが安心して働ける環境づくりを目指す姿勢に、企業としての誠実さを感じました。