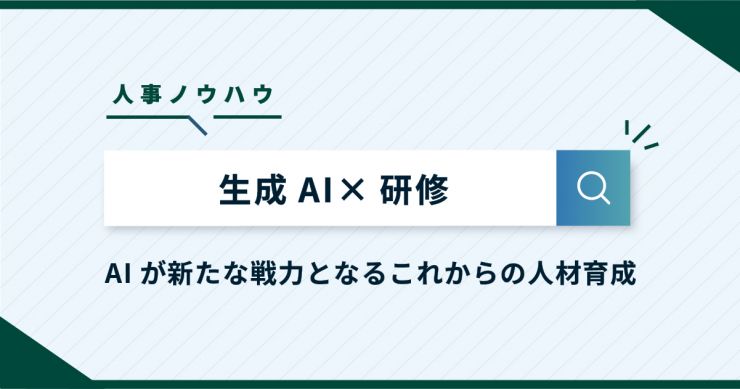ビジネスの現場において、AIの進化が、私たちの働き方を根本から変えようとしています。しかし、その変化は必ずしも組織の中で均一に進んでいるわけではありません。一部の従業員がAIを使いこなし生産性を上げる一方で、組織全体での活用は多くの企業が課題としています。
この変化の時代に、人事部はどのような役割を果たすべきなのでしょうか。
本稿では、AIを単なるツールとしてではなく、企業を成長させるパートナーとして捉え、これからの人材要件の定義、育成体系、そして現場での活用の仕組みづくりまで、人事部が主導すべき具体的なアクションを解説します。
1分サマリ
・AIはもはや単なるツールではなく、自律的に業務をこなす「デジタル労働力」となり、企業の人材戦略に大きな変革が迫られます。
・AIの台頭により、「実行力」や「仮説構築力」といった、AIには代替できない人間ならではの5つの価値が、これまで以上に重要になります。
・これからの人事部は、AI活用で生まれた時間を「個別化」された育成に充て、社員一人ひとりが持つ人間的価値を最大限に引き出す役割を担います。
・人事部は「人材要件の再定義」「HRBPへの進化」「AIエージェントのマネジメント」という3つの施策を主導し、AIと人が協働する未来の組織をデザインしていくことが求められます。
AIが「デジタル労働力」になる未来
これまで多くの企業で、AIは業務を効率化するための「便利なツール」として認識されてきたのではないでしょうか。しかし、生成AIの進化は、その認識を大きく覆そうとしています。もはやAIは、指示を待つだけの道具ではありません。自ら考え、判断し、業務を遂行する「デジタル労働力」として、私たちのすぐそばまで来ているのです。
自律的に稼働する「AIエージェント」の登場
たとえば、受信したメールの内容をAIが理解し、適切な返信案を作成する。さらには、定例レポートの作成を指示すれば、必要なデータを自動で収集・分析し、ドラフトを完成させてくれる。このように、特定の目的を与えられると自律的にタスクをこなすAIは「AIエージェント」と呼ばれ、ビジネスの現場で急速に存在感を増しています。
たとえば、Microsoft 365 Copilotが提供する特化型AIエージェント「Analyst」。社内で実施したエンゲージメントサーベイをインポートすると、AIが自動的に、所属別の経年傾向分析から相関分析まで自動で行い、経営層向けへの報告用レポートを数分で完成させます。
この変化は、単なる技術的な進歩にとどまりません。AIが自ら考え業務を遂行する「自律的な存在」になることは、企業における人と仕事の関係を根本から覆し、労働市場に大きな変革をもたらします。
事実、AIエージェントの普及と定着を見越して市場は急速に拡大中です。国内のITコンサルティング・調査会社ITRのレポートによれば、「日本のAIエージェント基盤市場は2024年度に前年度比8倍に急拡大し、2029年度には135億円に達すると予測されています。※」
この数字は、国内においてもAIエージェントが今後のビジネスで大きく存在感を増す未来を示しています。
※出典:ITRプレスリリース(2025年8月21日)https://www.itr.co.jp/topics/pr-20250821-1
人事部がマネジメントすべきは、もはや人間だけではない
これまで人事部は、採用、育成、配置といった活動を通じて、人間の従業員で構成される組織のパフォーマンスを最大化することに注力してきました。しかし、「デジタル労働力」が本格的に業務を担うようになれば、人間とAIが協働するハイブリッドな組織が当たり前になります。そのとき、人事部がマネジメントすべき対象は、もはや人間だけではなくなります。
生成AI時代に人事部が果たすべき真の役割
人間の能力を最大限に引き出し、AIとの最適な協働体制をデザインする。そして、AIを含めた新たな人材ポートフォリオを構築し、経営戦略に貢献する。これこそが、生成AI時代に人事部が果たすべき真の役割と言えるでしょう。
AIの導入は、人事部に「効率化」と「高度化」という二つの恩恵をもたらします。定型業務の自動化による時間創出(効率化)と、データ分析や示唆出しによる業務品質の向上(高度化)です。
これらによって生まれた貴重な時間やリソースを、人事部は何に使うべきか。その答えは明確です。AIには代替できない人間ならではの価値を、従業員一人ひとりが最大限に発揮できるよう、投資することです。
では、人間にしか発揮できない価値とは何でしょうか。
AI時代にこそ価値が高まる人間ならではの役割
AIが「デジタル労働力」として業務を担う未来は、私たちから仕事を奪うのではなく、人間が本来注力すべき役割を浮き彫りにします。AIがタスク処理の「What(何を)」や「How(どうやって)」を高速でこなすからこそ、私たち人間は、その業務に意味を与える「Why(なぜ)」を深く問い直すことが求められるのです。
これからの時代、人事部が向き合うべきなのは、AIには決して真似できない人間ならではの価値をいかに見出し、育んでいくかというテーマです。AIによる効率化の先にある、人材育成や人間ならではのコミュニケーションの重要性は、かつてないほど高まっていると言えるでしょう。
AIに代替されない「5つの人間的価値」
AI時代において人事部が育てるべき人材の指針となるのが、AIには代替できない、次の「5つの人間的価値」です。
1. 実行力
第一に、多様な関係者を巻き込み、物事を前に進める「実行力」です。AIがどれほど最適な戦略を提案しても、メンバーの協力を得てプロジェクトを推進し、目標を達成するのは人間の役割です。複雑な利害を調整し、チームを一つの方向に導く力は、今後ますます重要になります。
2. 仮説構築力
第二に、データや事象の奥にある本質を見抜く「仮説構築力」が挙げられます。たとえば、AIが提示した従業員アンケートの分析結果に対し、「エンゲージメント低下の根本原因は、実は新しい評価制度への納得感の低さにあるのではないか?」といった、経験則に基づく問いの起点を生み出す力です。AIが示す相関関係を鵜呑みにせず、解くべき真の課題は何かを発見する力こそが、人間の知性の見せ所です。
3. 共感力
第三に、相手の感情や環境を理解し、信頼関係を築く「共感力」です。1on1ミーティングで、部下が言葉にできない不安やキャリアへの悩みを表情や声のトーンから感じ取り、心に寄り添ったサポートを提案する。こうした温かみのあるコミュニケーションは、AIにはまだまだ難しい領域です。
4. 倫理観
第四に、複雑な状況で倫理に基づいた意思決定を下す「倫理観」です。AIが算出した人事評価の候補リストに対し、「この評価は特定の経歴を持つ従業員に不利益を生んでいないか?」といった公平性の観点から最終判断を下し、その判断に責任を持つ。これは人間にしか果たせない、極めて重要な役割です。
5. 専門知見
最後に、長年の経験で培われた暗黙知である「専門知見」です。これは、AIが提示した分析結果や選択肢について、経験というフィルターを通じその本質を見極める力と言えます。AIが「AとBの間に強い相関がある」と分析した結果に対し、「それは業界特有の慣習が背景にあるだけで、直接的な因果関係はない」と、AIの分析結果に人間ならではの文脈と意味を与え、より精度の高い意思決定を可能にします。
AI協働時代に人事部が主導すべき3つの具体的施策
ここからは、AIとの協働を前提とした未来に向けて、人事部が主導すべき3つの具体的な施策を見ていきましょう。
① 人材要件の再定義と育成体系のアップデート
まず取り組むべきは、自社にとっての「優秀な人材」の定義、すなわち人材要件そのものを見直すことです。ここで重要なのは、この定義は人間が行うべきだという点にあります。
AIは与えられた条件の中で最適化を行うことはできますが、「そもそもどのような人材が会社の未来に必要なのか」という根本的な問いを立て、新たな要件を定義するのは、まさしく人間の役割です。
たとえば、これまでの人材要件が「Excelスキル上級」だったとします。これからは、「データ分析でAIを使いこなし、的確な問いを立てられる能力」といったように、AIを使いこなすことを前提としたスキル要件へと変化していくでしょう。
そして、この新しい要件に基づいて、育成体系もアップデートする必要があります。その方向性は、必然的に「個別化」へと向かいます。
知識をインプットするような画一的な研修はAIに任せ、人事担当者はそれによって生まれた時間を、より付加価値の高い業務に集中させていくべきです。それは個々のスキルやキャリア志向に深く寄り添い、その人に合った価値の伸ばし方をデザインしていくことに他なりません。
AIとの協働を前提に、人間のポテンシャルを最大限に引き出すこと。これこそが、未来の人事部に課せられた使命と言えるでしょう。
② 事業と並走する「HRBP」への進化
次に、人事部のミッションそのものを、管理部門から事業部門の戦略的パートナー(HRBP)へと進化させることが求められます。待ちの姿勢で制度を運用するのではなく、事業戦略を深く理解し、能動的に課題を発見・解決する「攻めの人事」への転換です。
HRBPの重要な役割は、事業部門の懐に入り込み、現場の声に耳を傾け、ビジネス上の課題を特定することです。そして、「なぜこの問題が起きているのか」という原因の仮説を立て、現場の責任者や従業員と一体となって解決策を模索し、実行に移していきます。
この一連の活動は、AIには代替できません。多様な関係者を巻き込む「実行力」、データの裏にある本質を見抜く「仮説構築力」、現場の従業員の想いを汲み取る「共感力」など、前章で述べた人間ならではの価値が総合的に求められるのです。
AIに定型業務を任せられるようになるからこそ、人事担当者はこうした付加価値の高いHRBPとしての役割を強化し、事業の成長に直接貢献していくことが、これまで以上に強く期待されています。
③ 「AIエージェント」のマネジメント体制の構築
最後に、「AIエージェント」のマネジメント体制の構築です。なぜ、AIエージェントに人間のような「マネジメント」が必要なのでしょうか。それは、AIエージェントが一度導入すれば終わり、という買い切りのツールではないからです。
人間と同じように、AIエージェントにはライセンス料や運用費といったコストがかかり、その投資に見合う成果を出しているかを常に評価し、必要に応じて改善や入れ替えを検討する必要があります。また、ビジネス環境の変化に合わせて新たな情報を学習させ、パフォーマンスが安定するように調整するなど、人間でいう「能力開発」も必要です。
では、なぜそのマネジメントを、人事部が主導すべきなのでしょうか。
企業の目標達成に向けて、どのような能力を持つ人材を、どのように組み合わせ、配置するのが最適かを考える「人員計画」やその貢献度を公正に測る「評価制度」はまさしく人事の専門領域です。
たとえば、AIエージェントの成果をどう評価するのか。人間の業務を代替した「工数」で測るのか、あるいは、AIが生み出した「付加価値」で測るのか。こうした評価基準を設計し、運用していくことは、間違いなくこれからの人事部の新たな専門性となるでしょう。
情報システム部門と緊密に連携しながら、人事部がそのフレームワーク作りを主導することで、AIを真に組織の力に変えられると考えます。
AIを「デジタル労働力」と捉える以上、その管理には人事部の持つ専門性が不可欠です。これこそが、技術部門だけでは完結しない、人事部が未来の組織において果たすべき新たな価値と言えるでしょう。
変化の主導権を握り、未来の人事へ
AIの台頭は、人事部の皆さんの役割を大きく変えるでしょう。その変化の波に、戸惑いや不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、私たちはこの変化を、人事部がその専門性と価値をかつてないほど発揮できる絶好の機会と捉えてもよいのではないでしょうか。本コラムで繰り返し述べてきたように、定型業務をAIというパートナーに任せることで、私たち人間は、より創造的で、人の心に寄り添う、付加価値の高い仕事に集中できるようになります。
人間とAI、双方の強みを最大限に引き出す最適解を探求し、組織の未来をデザインする。その主導権を握り、企業の成長を力強く牽引していくことこそ、これからの人事部に与えられた、挑戦的でやりがいに満ちたミッションなのです。