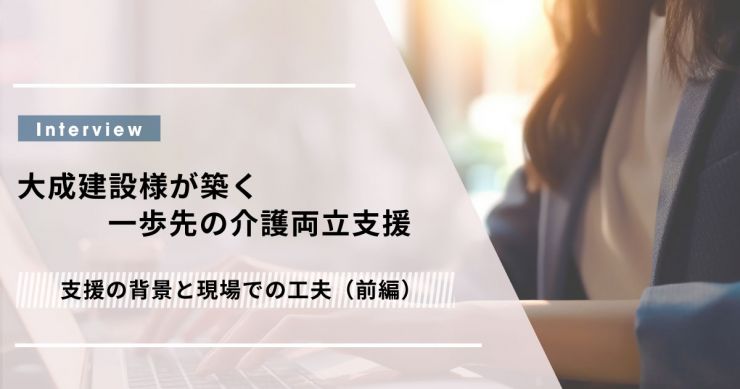2025年を迎え、団塊の世代がすべて75歳以上となったことから、高齢者の介護需要が急増すると想定されます。こうした中、家族の介護を理由に離職する「介護離職」への対応は、企業にとって喫緊の課題です。今後は、働きながら介護を担う“ビジネスケアラー”もさらに増える見込みであり、制度整備と職場環境づくりの両面で早急な対応が求められます。
大成建設株式会社(以下、大成建設)様は、2010年と早い時期から、介護と仕事の両立支援に取り組まれてきました。課題が顕在化する前に先手を打った同社の取り組みは、人材定着や組織力の強化にも繋がっています。
本対談では、管理本部 人事部 人財いきいき推進室 北迫 様にWHI総研角川・眞柴がインタビュー。大成建設様における制度設計の背景から現場での活用、社内文化の醸成、そして今後の展望までを伺いました。
前編となる本記事では、大成建設が2010年から先駆けて取り組んできた介護両立支援の背景と、その定着を支える現場での工夫に迫ります。
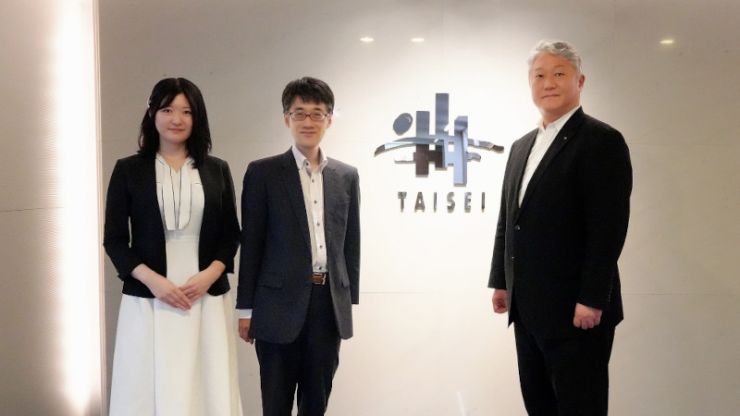
今回の対談者
北迫 泰行 様(写真右)
大成建設株式会社 管理本部 人事部人財いきいき推進室長
介護両立支援に早期着手した理由と背景
Q1. 介護両立支援に早くから着手された理由と背景を教えてください。
北迫様:
きっかけは、介護離職者が多かったからではありません。
2006年頃から公共投資の縮小により建設需要が低下し、業界全体に「従来型の働き方では持続できない」という危機感が広がっていました。当社でも、限られた人員で成果を出し続けるためには、一人ひとりがより柔軟に・生産的に働ける環境を整える必要があると考え、従業員の働き方を変える取り組みの必要性を強く感じていました。
その際、従業員に「柔軟で効率的な働き方を目指す上で不安に感じていることは何ですか?」とアンケートをとったところ、男女を問わず「家族の介護」が上位に挙がったのです。これが介護両立支援を始めた大きなきっかけでした。
この結果を受け、当時から40歳前後の従業員には当社で制作している「介護のしおり」を配付し、制度の周知を継続的に行ってきました。そのため、近年の法改正で周知が義務化された際にも特に困ることはありませんでした。
角川:
介護両立支援に本格的に取り組まれてから15年が経ちますが、きっかけは働き方改革だったのですね。
眞柴:
現在、介護を担っている従業員にはどのような属性や特徴があるのでしょうか。潜在的に該当する可能性のある層も含めて教えていただけますか。
北迫様:
従業員約1万人のうち、毎日または週に数回など、なんらかの介護を行っている従業員は約1割でした。
年代別では50代が最も多く、ついで60代以上、40代の順です。男女比は介護休暇の取得率に大きな差はありません。ただし、当社は男性従業員が8割を占めるため、同程度の取得率であっても、女性従業員の方が介護に直面している人数や負担は相対的に大きい可能性があると考えています。
角川:
やはり介護は、40代以降の幅広い年代で課題になりやすいのですね。
法改正をきっかけに制度を整える企業が多い中で、大成建設様は「何が従業員の働き方を阻害しているのか」という人事課題を先に洗い出し、対策を講じられてきた点が非常に先進的だと感じます。法改正への対応ももちろん重要ですが、課題を見極めて先手を打つ取り組みこそが、長期的な人材定着や組織力の向上に繋がっているのですね。
制度や支援策の認知・利用促進に向けた取り組み
Q2. 介護両立制度や支援策の認知・利用促進に向けた工夫について教えてください。
北迫様:
当社では、介護両立支援制度の認知向上を目的に、外部講師を招いた介護セミナーを定期的に開催し、制度や活用事例を紹介しています。
しかし、セミナー後のアンケートでは「制度があることを初めて知った」という声も依然として多く、制度の周知・定着には想像以上に時間がかかっているのが現状です。引き続き、さらなる周知方法の工夫が必要だと感じることも多いですね。
角川:
長年お取り組みを続けてこられているだけに、意外なお話です。やはり制度の認知や定着は、一朝一夕にはいかないのですね。
では、実際の制度利用状況についてもお聞かせください。特に、介護休暇や介護休業の取得状況はいかがでしょうか。
北迫様:
給与が出ない制度である介護休業を利用する従業員は非常に少なく、年間で2〜3人程度です。これは、当社が介護休暇を介護対象の人数にかかわらず年間20日間付与していることに加え、通常の年次有給休暇や最大80日間の積立有給休暇も活用できるためだと考えています。
会社としてもまずは毎年20日付与される介護休暇を利用するように促しています。その後に介護目的に適した積立有給、通常の年次有給と順に利用する感じです。
介護休暇を週単位や時間単位で取得する従業員は多く、2024年度は約300人が利用しており、年々増加傾向にあります。
介護休業については、法定よりも手厚く最長で180日まで取得可能としていますが、先ほど申し上げた休暇制度から先に利用されるため、実際の利用者は多くありませんね。
眞柴:
介護休業の利用が少ないということは、介護休暇などの制度が有効に機能している証拠のようにも感じるのですが、一方で、運用面や職場環境づくりに関しては、まだ課題と感じる部分はありますか。
北迫様:
制度自体は複雑ではありませんが、「使いづらい」という声があがることがあります。背景には、周囲に気を遣ってしまうことによる「言いにくさ」があるのだと思います。
介護セミナー後のアンケートでも、経済的な補助より「制度を使いやすい風土を作ってほしい」という要望が最も多く寄せられます。これはまさに「言いやすさ」や「お互い様の文化」をどう醸成していくかという課題です。
介護は誰にとっても将来起こり得ることで、最近では配偶者の介護に直面するケースも増えています。私自身も5〜6年間父の介護を経験し、現在は母の介護をしながら働いていますが、介護は本当に「ある日突然」やってくるものだと痛感しています。
角川:
制度の充実ももちろん大切ですが、それを安心して活用できる雰囲気や文化づくりが欠かせないのですね。

人材データの活用の現状と展望
Q3. 介護両立支援において、どのような人材データを活用していますか?
角川:
大成建設様では介護両立支援策を企画される際、どのような人材データを活用されましたか。
たとえば、従業員の経歴や勤怠情報なども考えられますが、特に効果的だったデータや分析の観点があれば教えてください。
北迫様:
当社の介護両立支援は、「働き方の改善を阻害する要因は何か」という視点からスタートしました。そのため、当時は勤怠情報や残業時間などの人材データは特に利用しませんでした。
現時点で明確な計画はありませんが、今後は活用を検討していきたいと考えています。
現在でも上司は部下との定期面談の中で、「親御さんの介護の心配はないか?」と声をかけてもらっていますが、親御さんの年齢と従業員の居住地(特に単身赴任が多い現場従業員の場合は親の住所との距離)を組み合わせて把握できれば、上司が定期面談の際に、例えば「遠距離に親御さんが住んでいるようだが、遠距離介護の心配はないか」といった具体的な声かけを行う際の参考になります。
また、公開範囲に配慮するという前提のもと、ストレスチェックや健康診断の結果と連携できれば、介護によるストレスへの脆弱性を事前に把握し、早期の支援に繋げられる可能性もあると考えています。
遠距離介護の実態などを可視化することで、会社として経済的補助などの施策立案にも活かせると思うのです。
角川:
介護両立支援では、人材データの活用がこれからさらに広がっていくと感じます。客観的な指標を施策に取り入れることで、的確な声かけや制度設計の改善に繋がりますし、制度や風土づくりと組み合わせることで、よりきめ細やかな支援が可能になりそうですね。
管理職の役割と個別対応策
Q4.介護当事者となる可能性が高い、40代以降の管理職向けに、特化した研修や支援策はありますか。
北迫様:
現状では、管理職に特化した研修はありませんが、管理職研修の中で約15分間を確保し、介護離職防止の取り組みや制度内容について説明しています。
その中で、部下から相談を受ける可能性や、自らも介護に直面する可能性があることを伝え、「介護支援はマネジメントであり、介護は自分事でもある」として意識してもらうよう促しています。
研修参加者には必ず「介護のしおり」を郵送しており、「研修で聞いた内容を覚えていたので、部下から相談を受けたときに対応できた」という声も寄せられています。
今後は、管理職自身が介護に直面した場合や、部下からの相談に対応する際のポイントをテーマにした、管理職向けの専門研修も実施してみたいと考えています。
眞柴:
まさに「備えあれば憂いなし」ですね。管理職自身の介護や部下の支援に備え、人事部門として研修を通じて意識醸成を行われているのですね。
北迫様:
そうですね。当部署はもともと障がい者支援や育児支援も担当しており、多様性を尊重した働き方を推進しています。介護は一見プライベートなことですが、従業員の離職防止や組織マネジメントの観点から企業にとっても非常に重要です。
日本人は控えめで自分からは言い出しにくい傾向があると感じるのですが、だからこそ上司が「大丈夫か」と積極的に声をかけることが大切だと考えています。
前編では、大成建設様が従業員一人ひとりにとって安心して働き続けられる環境をどのように築いてきたのか、その背景や企業としての強い覚悟に迫りました。
後編では、現場での具体的な取り組みや、介護と仕事の両立支援がもたらす成果について、さらに深く掘り下げてご紹介します。