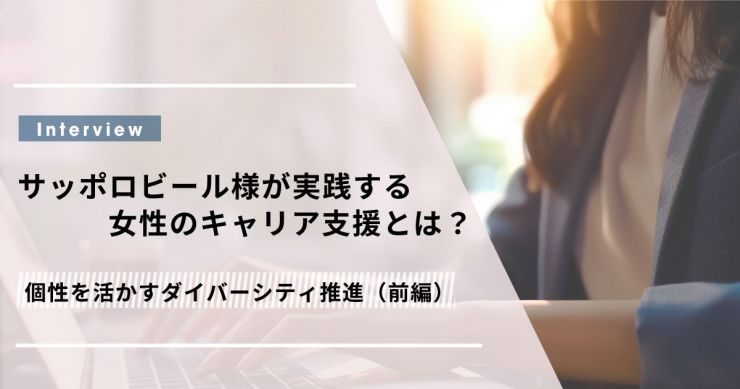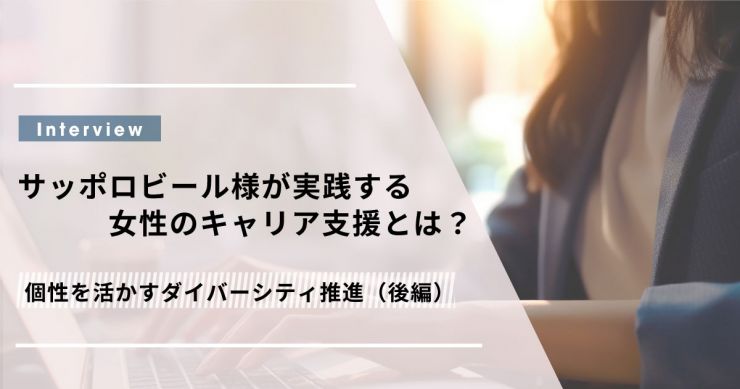酒類を国内や海外で製造・販売しているサッポロビール様では、グループの経営理念として「潤いを創造し 豊かさに貢献する」を掲げています。この経営理念を実現するために、ダイバーシティ推進に取り組んでおり、女性の活躍を促すための様々な取り組みを実施しています。
本対談では、サッポロビール株式会社様の高田様、宮澤様、傳田様、直江様にWHI総研(※1)の井上がインタビュー。女性活躍を推進する上での課題や人事施策を取材しました。
前半となる本記事では、サッポロビール様が女性活躍を推進する理由や現在の課題、またそれに対する具体的な施策についてご紹介します。
(※1)WHI総研:当社製品「COMPANY」の約1,200法人グループの利用実績を通して、大手法人人事部の人事制度設計や業務改善ノウハウの集約・分析・提言を行う組織

今回の対談者
(写真左から)
宮澤 悠 様 / サッポロビール株式会社 人事総務部 マネージャー
直江 伸夫 様 / サッポロビール株式会社 人事総務部 アシスタントマネージャー
傳田 法子 様 / サッポロビール株式会社 人事総務部 マネージャー
高田 塁 様 / サッポロビール株式会社 人事総務部 人事企画・D&Iグループリーダー
多様性を尊重して個性を発揮できる環境づくり
Q1. サッポロビール様では、2010年をダイバーシティ元年とし、女性活躍推進に取り組んでこられました。女性活躍推進に積極的に取り組む理由と背景を教えてください。
高田様:
サッポロビールをはじめとしたサッポログループでは「潤いを創造し 豊かさに貢献する」を経営理念としていますが、これを実現するためには、一人ひとりがお互いの違いを認めて、それを強さにしていくということが重要だと考えています。
また、サッポログループでは、経営理念を実現するうえで “いかにイノベーションを起こしてお客様に価値を提供するか” を重視しており、価値創出のため「多様性の尊重」を長年の経営課題としてきました。
多様性の尊重には様々な観点がありますが「女性」においては、“女性が継続して働きがいをもって活躍していることが当たり前な状態” を目指すべきだと考えています。
2010年当時は、女性従業員が出産や育児、結婚、配偶者の転勤等で、当社を退職することがまだありました。長く働きたいと思っている女性従業員がいても、ライフイベントによる中断で、結果的にやめざるを得なかった事例もあったので、そこをどうやって変えられるのかということも、ダイバーシティ元年以降、経営課題として考えるようになったという背景はあります。
井上:
経営理念の実現のために、一つはイノベーション、もう一つは育児等のライフイベントで従業員がやめないようにするということが大きな目的なのですね。この目的のために、サッポロビール様では、従業員が働き続けられるようなしくみを作られています。それについて詳しくおうかがいします。
Q2. 女性のキャリアを中断させないためにどのような制度を導入されていますか。制度の概要や導入背景を教えてください。
傳田様:
当社では、育児や介護等の事情がある方が勤務地を限定して働ける「NR制度」を2016年より導入しています。
「N」は全国転勤有りのナショナル型、「R」は勤務地を特定のブロックに限定できるリージョナル型で、育児や介護、本人・配偶者が病気になってしまった場合でもリージョナル型を選択することで家庭とキャリアを両立させることができます。
しかし、リージョナル型の場合、ブロックによって従事できる業務が限定されていました。そのため、スキルを高めるためにブロック外の業務をしたくても希望の業務ができないケースもあり、“男女に関わらず、継続して働きがいをもって活躍している” とは必ずしも言い切れない状態でした。
この課題を解決するため、2024年に「リージョナル型社員のどこでも勤務制度(以下、どこでも勤務制度)」という、居住ブロック以外の業務をテレワーク中心で遂行できる制度を導入しました。
これによって、たとえば、配偶者の転勤等で勤務地を変更する場合でも、実施条件を満たせば、業務内容を変更せずに継続できるようになりました。
2024年3月に導入したばかりですが、すでに数名がどこでも勤務制度を利用しており、希望の業務を続けながら、家庭とキャリアを両立することができています。
井上:
育児や介護のためにやりたい仕事を我慢するということになりがちですが、どこでも勤務制度を使えば、育児や介護をやりながら自分のキャリアも諦めないということが実現可能ですね。
パートナーの転勤で一緒に居住地を移ることは性別関係なくあり得ると思うのですが、どこでも勤務制度は男女ともに利用できる制度なのでしょうか。
高田様:
男女どちらも利用できます。この業務はこの場所でしかできないという固定観念を変えるきっかけにもなるんじゃないかと思っています。男女関係なく、業務をするうえで場所にとらわれない視点が生まれはじめていて、意識変革に繋がっています。
井上:
男女関係なく、やりがいを持って働き続けられる環境がサッポロビール様にはあるのですね。

全従業員が活躍できる女性活躍推進への取り組み
Q3. 部署や職種によって、男女の偏りはありますか
宮澤様:
サッポロビールには、飲食店様に当社商品をお届けする業務用営業という部署があるのですが、ここに所属する女性従業員が少ない状態です。
女性のお客様も増やしていきたいという飲食店様のニーズがある中で、業務用営業にも女性視点が求められていますが、その視点を十分に取り入れられていないことは課題だと考えています。
一方で、同じ営業でもスーパーやコンビニ等、小売業のお客様に営業する流通営業という部署もあるのですが、業務のやり方が異なるため、業務用営業と比べると女性従業員や女性管理職の人数が多いという状況です。
当社としては、こういった部署間の男女の偏りを解消して、女性管理職比率全体の向上に繋げたいと思っています。
井上:
同じ営業でも男女の偏りが生まれているのですね。工場や技術系も女性が少ないイメージがどうしてもあるのですが、いかがでしょうか。
宮澤様:
生産技術部門や工場については、そもそも採用時点で技術系を考えている女性の母数が少ないです。会社として女性の技術系を採用したいと思っても母集団がいないので、どうしても男性に比べると少なくなります。
そのような中でも、若手では女性の技術系の従業員が増えてきました。最近では女性の工場長も誕生しています。ただ、まだまだ男性が多い職場ですので、今後さらに技術系の女性管理職を増やしていきたいと考えています。
これに対して、研究職であるR&D系では、女性が多く活躍している状況であり、そこまで男女比率に差がなく、管理職も生まれています。
井上:
生産技術系の女性は少ない一方、研究開発系では男女の差があまりないのですね。配置の課題については、会社で主導して女性に様々な業務を経験してもらうことも可能だと思いますが、会社としてジョブローテーションを積極的に行う考えはあるのでしょうか。
宮澤様:
人事としては、できるだけ女性管理職を増やしていきたいという思いは当然あって、それを実現するような配置をしています。また、現場から一度本社に異動した女性も、ずっと本社部門でキャリアを積むのではなく、もう一度現場に戻ってもらうこともあります。これは男性も同様です。
多様な業務を経験してもらえるよう、そのような配属を意識的に進めており、女性従業員が活躍できる異動配置を考えているところです。
Q4. 女性管理職を育成するうえで、どのような取り組みをされているか教えてください。
宮澤様:
当社では人財育成会議という、各従業員が成長するための課題について、役職者が集まって意見を出し合う場を設けています。女性管理職を育成するという観点では、この人財育成会議において、女性の管理職候補者をリストアップし、対象となる人財をどのように育成していくのかを議論しています。
今まではそのような時間を明確にとっていたわけではなかったのですが、人事から、必ず女性管理職の育成について議論してくださいと事業場長に依頼をして、しっかり時間をとって話してもらうようにしました。
女性を優遇するわけでなく、女性が活躍しやすい環境を整えるためにどうするか、また成長スピードを上げてもらうためにどうすべきかを話し合ってもらうことが目的です。やり始めたばかりではありますが、人事としても、現場にこれを浸透させていくつもりです。
井上:
人事総務部が積極的に現場に働きかけて女性活躍を後押ししているところが、サッポロビール様の特色ですね。
現場に理解してもらうというのは非常に大変なことかと思いますが、具体的には説明会を開くといったような取り組みもされたのでしょうか。
高田様:
2023年から2026年の中期経営計画のなかで、女性管理職比率の向上を重点目標としており、昨年は部長クラスの方に向けて、女性従業員の早期育成に関する説明会を実施しました。
井上:
現場からはどのような声が上がっているのでしょうか。
高田様:
やはり一番声が上がるのは、女性を優遇することで、男性従業員が不利益を被るのではないかという意見です。
人事総務部として、これまで男女問わず人財育成に取り組んでいただきたいというメッセージを管理職に伝えています。ただ、女性の場合は、出産や育児というライフイベントによるブランクが生じやすいため、そのブランクをあらかじめ考慮したうえで、早期に育成する必要があると考えています。
しかし、女性管理職の早期育成に取り組むことが、女性を優遇して管理職に昇格させることだと誤解をされることもあるので、女性管理職の早期育成の必要性について繰り返し説明するようにしています。
井上:
決して男女区別しているというわけではなく、あくまでライフイベントでブランクが発生しやすい女性を早期から育成していくということですね。

Q5.管理職の評価項目に「ダイバーシティ」を導入された狙いと、実際どのような形で評価されているか教えてください。
高田様:
管理職の行動面を見る評価の中に「ダイバーシティ&インクルージョン」という評価項目を入れています。
この項目では、管理職としてダイバーシティ&インクルージョンを意識して日頃から行動し、具体的に働きかけをしているかを見ています。
評価項目は会社から従業員へのメッセージと考えています。ダイバーシティ&インクルージョンが経営課題であることをより理解してもらうために、項目に入れたという背景があります。
井上:
ダイバーシティ&インクルージョンを重視しているというメッセージを伝えても、従業員からなかなか理解されないこともあるかと思いますので、評価項目として伝えていくのは効果的ですよね。
しかし、ダイバーシティ&インクルージョンは営業のように明確な数字があるわけではなく、評価が難しい項目のようにも感じています。貴社ではどのように運用されているのでしょうか。
宮澤様:
管理職であれば当然ダイバーシティ&インクルージョンの視点を持ち合わせているべきなので、項目に入れたものの「できたらすごい」ではなく「できて当たり前」というように見ています。
ただ正直に言うと、運用面においては基準を明確にすることが難しい部分もあり、人財育成会議の中でも重点的に議論するかというと、正直まだそこまで進んでいない状態です。
会社としてもっと意識してもらえるように打ち出すのであれば、ダイバーシティ&インクルージョンについて具体的にどんな行動をするかという詳細な行動にまで落とし込む必要があると考えています。
高田様:
実際はまさに多様性を「尊重する・理解する・活かす」といった姿勢をもっているかが評価の基準になっています。
また、年1回の管理職層の360度評価でもダイバーシティ&インクルージョンを評価項目として入れています。360度評価は人事評価とは別で、本人の育成を主な目的とした施策です。
井上:
メッセージを従業員に伝えていくための工夫やお取り組みが素晴らしいですね。