2,400名の評価集計をデータ統一で大幅短縮。
人材育成を実現する一歩に

写真左より:人事教育部 執行役員 部長 田中 康義 様、次長 古田 健 様

- 法人名
- 株式会社TKC
- 本社所在地
- 〒320-8644
栃木県宇都宮市鶴田町1758番地 - 設立
- 1966年10月22日
- 資本金
- 57億円(2023年1月時点)
- 主な事業内容
- 国内の会計事務所(税理士事務所、税理士法人および税理士業務に従事する公認会計士事務所)に対する情報サービスと、地方公共団体(市町村等)に対する情報サービスの提供およびソフトウェア開発等
1966年の創業から一貫して国内の会計事務所および地方公共団体に対して情報サービスを提供し、業界での知名度が非常に高いTKC様。クライアントとの密な業務推進のため、各都道府県のほぼすべてに100ほどの事業所があり、2,400名以上の従業員が活躍されています。
2020年9月に「COMPANY人事」「COMPANY Web Service」を導入いただき、抜本的な人事業務の見直しを行いながら着実にシステム設計を行い、2022年5月、COMPANYの本格的な運用に至りました。
課題
・データ加工に時間かかり適材適所を考える時間がない
・表計算ソフトに詳しい人へ業務が属人化している
採用理由
・大手企業に数多く採用されてきた実績と業務に関する気付きを他社事例から学べるネットワーク
効果
・データを統一し、全員が同じものを見られる環境に
・特別な知識やスキルなしで設定でき、人的ミスも削減
導入の経緯データ加工に割く時間を削減し、データを中心に「考える」時間を捻出したい
――まず、人事システムをCOMPANYへ切り替えることになった経緯をお聞かせください。
田中様:
以前のシステムで人事データを利用する際は、用途に応じて表計算ソフトのデータを切り出し、加工する必要がありました。このため、見栄えのよいグラフ作成や加工スピードをあげるために表計算ソフトのスキルを磨くことに没頭し、データ加工の作業工数が多い状況でした。データをベースにした適材適所を考えるところにまで目を向ける余裕が、時間的にも、意識的にも不足していました。
また、以前のシステムはIDとパスワードを一人ひとりに付与する仕様だったため、組織変動や人事異動のたびに面倒なライセンス管理をする必要がありました。このため、ライセンス付与される人数が限定的になり、一部の上位管理者しかシステムにアクセスできなかったのです。
人事データ活用が一部の上位管理者または表計算ソフトに詳しい人に属人化されることは、企業として正しい状態とは言えません。そこで、関係者が誰でも人事データにアクセスでき、無駄な作業をすることなく考える材料を提供するシステムが必要だと考えました。
採用の理由多くの大手企業に使われている事実がもたらす信頼と期待
――COMPANYを知ったきっかけや採用の決め手はありますか。
田中様:
様々なシステムを見ましたが、一言でいうならば実績が理由です。小規模の企業で使われている人事システムは多くありますが、COMPANYは主に大規模な企業で使われており、継続年数も長い点に惹かれました。これはつまり、非常に多くのユーザーとかかわり、ユーザーが直面してきた大量の課題を長きにわたり解決してきたと推測しました。
当時、私は人事教育部に異動してまだ1~2年しか経っておらず、人事のことも人事システムのことも、わからないことが多くありました。ですが、COMPANYなら多くのユーザーが同じ人事業務をこなしているので、未経験のことも誰かがすでに解決し、システムの使い勝手や仕様の面でも洗練されているはずだと思いました。
これには私たちの業務プロセスに関する気付きを他社事例から学べるのでは、という期待も含まれています。今の業務プロセスを改善できる余地があるのならば、システム設計で無理に解決することは得策ではありません。他社事例に倣って、社内の体制やしくみを見直すことで持続可能な業務改善になると考えています。COMPANYはユーザー間の交流も活発ですし、非常に期待しています。

写真:人事教育部 執行役員 部長 田中 様
導入の効果必要な情報を正確かつ迅速に抽出。2,400名以上の集計工数を2日短縮
――COMPANY人事の導入で、どのような効果を感じていらっしゃいますか。
古田様:
COMPANY導入後は、様々なシーンで業務を改善できました。
たとえば、旧システムでは最新の人事情報しか記録できなかったため、過去の履歴は都度、表計算ソフトでデータ保存・管理する必要がありました。従業員のキャリアを知りたくてもデータ検索の手間がかかり、最新データがどれなのかわかりにくい状況でした。
COMPANYの場合、従業員一人ひとりの人事情報を時系列で保管できるため、どの時点の履歴でも簡単に引き出せるようになりました。一人分のファイル保存や検索は大した作業ではありませんが、2,400名以上ともなると大きな差になります。
――COMPANY Web Serviceも導入いただきましたが、こちらの効果はどうでしょうか。
特に賞与評価の際に、COMPANY Web Serviceの効果を感じています。
以前は全従業員が各自で表計算ソフトを用いてファイルを作成し、目標達成率と組織貢献度評価を入力していました。入力したデータが部門長に提出されると、部門長は部下のファイルをすべてまとめて1つのブックにしなければいけませんでした。
その後、まとめたファイルが部門長から人事部門へ提出され、人事部門は集計作業を実施します。しかし、マクロの不具合や社員番号、名前の記入ミスで集計がうまくいかないことが多々ありました。修正を繰り返し使用されてきた集計マクロの詳細は、設計者にしかわからない部分が多くあるため、エラーが出てしまうと原因究明に想像以上の時間を要します。マクロに問題がなくても、人的ミスがエラー原因だったことも多くありました。賞与の時期はこうした対応に毎回かなりの労力を費やしており、人事部門における精神的負荷も高くなっていました。
これらの業務負荷はCOMPANYによって一気に解消されました。COMPANYでは集計ルールを設定する際に特別な知識やスキルは必要とせず、社員番号や名前は自動的に入力されるため人的ミスも最大限なくすことができます。各従業員が入力したデータは適切なアクセス制限の下、COMPANYに直接集約されますので、部門長に部下のデータをまとめてもらう必要もありません。
実際に部門長からも無意味な作業がなくなり、楽になったという声があがっています。賞与評価の集計作業は、以前と比較して2日は短縮できているように感じています。

写真:人事教育部 次長 古田 様
――他社事例や業務改善についてもご期待されていましたが、この点はいかがでしょうか。
田中様:
年に一度、基本給を決めるための職務考課があるのですが、その際の評価基準を示した「職務考課表」が、以前は35種類ほど存在していました。
ですが、COMPANY導入時、立ち上げをサポートしてくださったコンサルタントさんから、「これほど多いケースは稀である」と指摘を受け、他社と比較してTKCの状況が不自然であることに気付きました。
社内に向けて状況を説明する際にも、1,500ものCOMPANYユーザー企業(ほぼ上場企業)においてTKCほど職務考課表の種類が多い企業はない、と伝えるだけで非常に説得力がありましたね。
活用の方針従業員一人ひとりに注目した人材育成と適材適所を考えていきたい
――最後に、今後の展望や目指したい姿をお聞かせください。
田中様:
COMPANYの導入によってデータを統一し、全員が同じものを見られる環境が整いました。今後は、従業員一人ひとりに注目して適材適所と人材育成(タレントマネジメント)を、全員で考えていきたいです。過去の役職や実績だけでなく、学びや成果まで見たうえで、次のチャレンジや評価を議論していけたらと思っています。これからの人事工数は、COMPANYを真ん中において皆で見ながら考える時間に充てたいですね。
古田様:
一定のスキルと知識があれば、誰でも人事業務ができるようになるのが次のゴールと思っています。今までは表計算ソフトの習熟度が高い従業員に人事業務が集中していましたが、これからは一定の知識とCOMPANYのマニュアルがあれば、誰でも作業ができます。
その先に、田中から話があった適材適所やタレントマネジメントにさらに時間を割けるようになります。そのためには土台が必要で、その核になるのはCOMPANYだと思っています。
※本記事は2023年1月時点の内容です。
業種
従業員規模
関連する導入事例
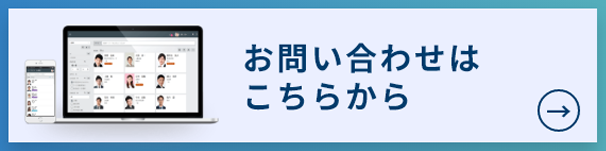
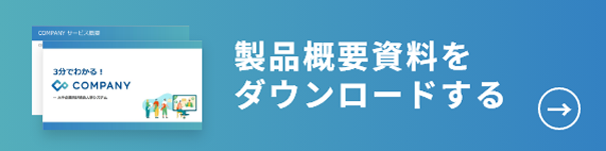

カテゴリから導入事例を探す
- 業種
- 従業員規模
- 目的・課題
業種
- 全て
- 陸運
- 輸送用機器
- 鉄鋼
- 製薬
- 小売・流通
- 公共
- 建設
- 教育
- 協同組合
- 化学
- 医療・福祉
- メーカー
- IT
- サービス
- その他業種
従業員規模
- 全て
- ~2,000名
- 2,001~5,000名
- 5,001~10,000名
- 10,001名~
目的・課題
- 全て
- クラウド化
- システム連携・一元化
- システム老朽化・使いにくさの解消
- スマホ・マルチデバイス対応
- ペーパーレス化
- 業務効率化・管理コスト削減
- 人材育成・キャリア支援
- 人事データ分析・可視化
- 多様な勤務形態の管理
- 適材適所の人材配置
- 独自制度への対応
- 変化に対する柔軟な対応
- 従業員エンゲージメント
- 過重労働の防止
- グループ会社のシステム基盤統一







