人材スキルの可視化から組織力を分析。
個人と組織が共に成長するために

写真左より:人事部 人材開発グループ 副調査役 下柿元 貴章 様、人事グループ 副調査役 大迫 航 様、人事厚生グループ 安楽 優香 様、人事グループ 主任調査役 東郷 哲也 様

- 法人名
- 株式会社鹿児島銀行
- 本社所在地
- 鹿児島県鹿児島市金生町6番6号
- 設立
- 1879年(明治12年)10月6日
- 資本金
- 181億3,000万円(2024年4月1日現在)
- 従業員数
- 2,090名(2024年4月1日現在)
- 主な事業内容
- 金融(銀行業)
創業145年の長い歴史をもち、九州フィナンシャルグループをけん引する存在である鹿児島銀行様。離島地域にも支店を構え、ユーザー数15万人超のキャッシュレス決済「Payどん」を展開するなど、その事業は地域住民の生活に深く根付いています。
同行は2023年4月、新人事制度と共にCOMPANYを運用開始。タレントマネジメント、人事給与、勤怠管理と人事関連業務に幅広く活用されています。特に人的資本マネジメントへの取り組みに注力されており、COMPANYを利用した各種施策についてお話しいただきました。
課題
・ベンダーによる更新作業と追加コストを要する旧人事システム
・法改正や税制改正に加え、流動的な人事制度への対応に懸念
採用理由
・パッケージでありながら細やかな設定が可能
・大手日本企業への豊富な導入実績
効果
・従業員のスキル調査を分析し、各営業店の総合力を可視化
・営業店での人材育成や適材適所により組織全体の能力向上へ
――まずは皆様のご担当業務についてお聞かせいただけますか。
東郷様:
私は、2021年に新設された人事改革室のプロジェクト統括責任者として、新人事制度の確立を推進してきました。同時にCOMPANY導入も実施することとなったため、導入プロジェクトチームと足並みをそろえて取り組んできました。
大迫様:
私はCOMPANYの導入決定に伴い、システム担当として2022年4月に人事部へ配属されました。現在も人事としての定常業務、システムの運用を主に担当しています。
下柿元様:
私は2年前より人事部人材開発グループのリーダーとして、従業員の研修、資格試験の管理など、育成全般を担っております。COMPANYの導入に際しては主にタレントマネジメント(CTM)の部分に携わりました。
安楽様:
私は人事厚生グループで、主に給与、勤怠、福利厚生を担う仕事をしております。今回のプロジェクトでは、COMPANYでの勤怠登録と申請関係を設定しました。
人事には4年ほどおり、給与や勤怠を担当してきたのですが、システム設定に携わるのは初めてのことで、Works Human Intelligenceさんに助けられて乗り越えてきました。
導入製品 : CJK、CWS、CSR、CTM
● CJK (COMPANY人事・給与) :COMPANYの基本機能で、人事データ管理や給与計算等を実施
● CWS (COMPANY Web Service) :ポータルサイトを通じて従業員が様々な申請を行うためのしくみ
● CSR (COMPANY就労・プロジェクト管理) :様々な働き方に対応した打刻や休暇等の勤怠・労務管理機能
● CTM (COMPANY Talent Management) :人員検索・配置、ポジション管理、スキル管理、サーベイ、人事KPI、人的資本情報開示といった人的資本マネジメント機能
導入の経緯従業員の声を最大限に反映した柔軟な新人事制度の確立
――2023年4月より新人事制度がスタートしたと伺っていますが、15年ぶりの大プロジェクトだったそうですね。どのような背景があったのでしょうか。
大迫様:
鹿児島銀行は、本業で地域のお役に立つ一方で、新規事業や働き方改革といった面でも地元企業をリードし、新しい取り組みを広げていくべきだと考えています。
当行では、働き方、女性活躍、子育て、健康経営といった人的資本に関わる部分を特に重要視し、制度改定を含め様々な施策を企画・実施しています。
たとえば、女性管理職の比率はまだ十分とは言えない状況です。単に昇進させればよいというものではありませんので、まずは地固めとして、女性が結婚、出産後も無理なく働けるような環境を整えました。2017年には厚生労働省の「子育てサポート企業」の認定も受けています。
東郷様:
女性の働きやすい環境作りという点では、女性のドレスコードを廃止し、ビジネスカジュアルを推進しています。今、制服を着用している女性行員はいません。
この取組みは、ジェンダー平等の観点からも、九州フィナンシャルグループ全体で実施しています。
――新人事制度の確立には2年を要したとのことですが、どのような点に留意されて作られたのでしょうか。
東郷様:
仕事に対する考え方や就業観などが変わってきている中で、経営陣には「従来の人事制度は時代に合っていないのでは?」という危機意識がありました。このため、新人事制度に着手する際は「とにかく従業員の声に耳を傾けるように」と指示されていました。
中期経営計画の策定や、ビジネスカジュアルの導入、副業解禁など様々な施策を実施してきましたが、すべてのプロジェクトにおいて全従業員にアンケートを取っています。従業員の声をすべて吸い上げ、経営陣に都度報告をしながら戦略や制度を作ってきました。
――新人事制度の具体的な内容を教えていただけますか。
東郷様:
そうですね、今回の大きな変更としては、勤務地について「エリア限定」と「エリアフリー」を選択できる制度の導入があります。広域展開している当行ならではの事情を鑑みた結果、勤務地を自宅から通勤可能な範囲で選べる働き方と、勤務地を限定しない働き方のどちらかを選べるようにしました。
当然、鹿児島市内といった利便性の高いエリアを選択する従業員が多くなるのではないかという懸念があり、経営陣からもたびたび質問が寄せられました。これに対しては、「エリア限定」と「エリアフリー」において給与面での待遇に差を設けることで、極端な偏りを避けることができました。大迫が様々な待遇パターンのシミュレーションを繰り返したおかげです。
もう少し具体的に言いますと、「エリアフリー」の従業員にはエリアフリー給を支給し、中でも地理的条件が厳しいとされる地域の手当については、手厚くしています。エリア限定であれば無理なく働けるという従業員をサポートしつつ、エリアフリーの従業員も納得できる制度にしたわけです。
また、営業目標を持たず、事務を主に担当する「特定職コース」を設定しました。
特徴的なのは、この「特定職コース」は一時的に選択することも可能な点です。育児や介護といった一定期間だけ特定職コースに切り替え、ひと段落したらまた総合職コースに戻ってこられるというように、ライフイベントに合わせて柔軟に働き方を切り替えられるようにしました。
大迫様:
この新人事制度は、外部からも高く評価していただいています。最近ですと、2023年5月に全国22の県が加盟する「日本創生のための将来世代応援知事同盟」から最優秀将来世代応援企業賞をいただきました。いくつか受賞理由がある中でも、今回の新人事制度が特に大きな評価ポイントになっているようです。

人事部 人事改革室 室長 東郷 哲也 様
選定の理由社内外の変化にスムーズかつ追加費用なしで追従するには
――今回、どのような理由で長い間ご利用されていた人事システムを見直すに至ったのでしょうか。
大迫様:
従来の人事システムはオンプレミスで稼動するパッケージ製品で、当行の業務に合わせてかなりカスタマイズが加えられていました。導入から15年が経過し、日々の運用自体は非常に安定していたのですが、毎年の法改正や税制改正への対応に懸念がありました。
通常のシステムバージョンアップでは賄えず、ベンダーさんに都度、コストと時間をかけて更新してもらわねばならなかったのです。
こうした法改正などの環境変化や、人事制度の改定といった社内での新たな試みに対して脆弱性を感じていました。働き方改革が広まり、人事制度も流動的になっていく中で、将来的に当行のやりたいこと・やらねばならないことに、このシステムはスピーディに対応できるのか、できたとしても費用面での負荷はどうなるのか、といったことを検討しました。結果、人事システムについてもこのタイミングで見直すべきだという結論に至ったのです。
――流動的な将来を見越しての見直しだったのですね。では、数あるシステムの中でCOMPANYを選んでいただいた理由は何だったのでしょうか。
大迫様:
それについては、大きく3つ挙げられます。
まず1つめは「クラウドサービスである」ことですね。サーバー設置やシステム組み込みといった初期コストがかからず、スピーディな導入ができることが必須条件でした。
同グループ内の肥後銀行と当行は、それぞれ別の人事システムを運用していますが、将来的にはシステム統合も進めていきたいと考えているので、統合のしやすさという点においても、クラウドシステムであるほうが良いと思っていました。
COMPANYはクラウドシステム(SaaS)である点に加え、法改正への対応が無償バージョンアップという形で自動的に実施されるので、変化への対応スピードと追加コストがかからない点も魅力的でした。
2つめは今までベンダーさんに任せざるを得なかった改修を自分たちでできることです。もちろんその分の工数はかかってしまうのですが、以前の人事システムはあまりにもカスタマイズされすぎていて、自分たちで手を入れられる箇所が非常に限定的でした。
まず見た目でどこが自分たちで変更可能な箇所なのかが分かりづらい。加えてカスタマイズ部分とパッケージ部分の資産が、当行とベンダーのどちらに属しているのかといった問題もあり、一見簡単そうな変更であってもベンダーさんに依頼しなければならないという事態も発生していました。
COMPANYはパッケージ製品であるにもかかわらず非常に細やかな設定が可能なので、当行の事情に合わせたカスタマイズができました。
3つめはやはり「実績」ですね。様々な業種において中規模以上の企業に導入実績があるという点が決め手でした。COMPANYは大手日本企業でのユーザーが多いと思いますが、そうなると汎用性よりも専門性が求められ、カスタマイズありきの構成になりがちですよね。そこであえて汎用性を重視しているところが大きかったです。

人事部 人事グループ 副調査役 大迫 航 様
導入の効果従業員スキルの可視化で各営業店の総合力の現状把握
――導入前と比較して何か違いを感じておられますか。
安楽様:
私が担当した「COMPANY就労・プロジェクト管理(CSR)」の勤怠情報については、画面を見た際に直感的で分かりやすいと感じています。従来のシステムはテキスト中心だったので、データの概要をつかむにも数字を追いかけながら「これくらいかな」と推量するような状況だったのですが、COMPANYではグラフや図が効果的に使われているので、パッと概況をつかめる気がします。

COMPANY就労・プロジェクト管理(CSR)「勤怠ダッシュボード」 イメージ
従業員が利用する勤怠ポータル画面も、様々な情報がシンプルに分かりやすく表示されていてとても良かったです。やはり当行の従業員が毎日使う画面・機能ですので、感覚だけで操作できるくらいシンプルなデザインが良いですよね。こちらについてはそれほど大きなカスタマイズはせず、初期設定のままでも十分使えています。

人事部 人事厚生グループ 安楽 優香 様
下柿元様:
私が担当した「COMPANYタレントマネジメント(CTM)」では、現在メンバー管理、キャリアシート、保有資格、研修などの情報を管理しています。人事考課なども新人事制度に伴って若干制度ややり方が変わっていますので、それに合わせて整えました。
CTM活用で特筆すべきは、営業店スキルの可視化をCTMを使って実施し、人材育成や適材適所、グループ間での人材活用につなげている点ですね。
――それはとても画期的ですね!人的資本マネジメントにおける先進的な取り組みだと思います。詳しく教えていただけますか。
下柿元様:
営業店の業務スキルを10項目に分けて、各従業員に0~5の6段階評価をしてもらうんです。支店長が結果をまとめ、私たち人事部門へ提出するという流れになります。
各営業店において10項目それぞれの基準値を設定しておくことで、自分の営業店はどのスキルに秀でているのか、もしくは基準に足りていないのか、を数値で認識できるわけです。
結果は「組織全体」「営業店」「個人(従業員)」の3つのフェーズで分析し、活用していくつもりです。
たとえば、「組織全体」の場合は、中期経営計画に沿った人材育成や適材適所ができているかをチェックできます。組織全体で弱い部分のスキル研修の強化計画を立てる、A営業店のスキル不足をB営業店から異動させることで補うといった戦力の戦略的配分、などの人事施策へ転じることができます。
「営業店」の場合は、各支店長へ結果をレーダーチャートにしてフィードバックすることで、支店長が客観的に自組織の不足スキルを認識できます。その結果、現場の目線でより細やかな人材育成計画や適材適所が実施できます。同時に管理職のスキルアップにもつながりますよね。
「個人(従業員)」の場合は、キャリアプランや目標の作成に役立ててもらうことで、従業員のモチベーションやエンゲージメント向上につながるのではないかと思っています。
また、こういった取り組みを定着させることで、「個人の評価、働き方を明瞭かつ丁寧にしてくれる企業」というイメージとなり、従業員の離職率低下や良い人材の採用にもつながればと期待しています。
第1回のスキル評価を2023年6月に実施し、以降、半年に1回実施しています。回を重ねるごとにデータ精度があがってきており、より適切な人事施策へ反映できるのではないかと期待しています。
――素晴らしいですね!一口に人的資本マネジメントといっても、実際の取り組みとなると各社各様で急に難しくなりがちな気がします。実際に運用にもっていくためのコツのようなものはありますか。
下柿元様:
振り返ってみると、スモールスタートを意識して実施したのが良かったのではないかなと思います。経営層からも「シンプルにやれ」と言われていたのですが、スキルを10項目というあえて大きな括りで分けたところがポイントですね。
お客様のニーズが多様化していますから、求められるスキルも本当はたくさんあるんです。でも100も200も項目を作ってしまったら、評価自体の負荷が大きすぎて形骸化のリスクが高くなります。思い切って10項目に絞ったことで、半年に一度の評価も従業員から不満の声もなく、しっかりと取り組んでくれています。
まずはスモールスタートを切って、走りながら改良していけばいい、という気持ちで進めています。

人事部 人材開発グループ 副調査役 下柿元 貴章 様
今後の展望可視化と分析を発展させることで、個人も組織も一緒に成長していく
――今後、鹿児島銀行の人事部門として、どのようなことを目指していきたいですか。またCOMPANYへのご要望や期待があれば、ぜひお聞かせください。
下柿元様:
営業店スキルの可視化と並行して、今、専門人材のスキル調査にも着手しています。
営業店スキルは、銀行員が本来やるべき業務で必要な能力を可視化するのですが、専門人材スキルというのは、事業承継やIT、法務といった特定の分野で必要とされるスキルのことです。
知識、経験、実績の3つの視点から専門人材スキルを定義し、専門人材の認定や育成をしていきたいと思っています。最終的に人材ポートフォリオを作りたいんですよね。
今、こうした取り組みを手作業で行っているので、CTMを使ってシステマチックにできないかなと考えています。
大迫様:
営業店スキルという言葉は30年以上前からあるくらいで、他銀行さんも一度は挑戦したことがあるんじゃないかなと思います。ただ、最適解が見つからず断念してしまったところが多そうな印象です。私たちのチャレンジがこの先も継続して成果を出すために、何に気をつけるべきなのか常に意識していますね。
注意すべきところとしては、先述した通り、最初から細かくやりすぎず、スモールスタートで始めて徐々に精度をあげていくようにすることと、集計や分析など運営に手間をかけずに実施できるよう環境を整えることだと思います。
CTMが、そういったスキル項目の深さや量を自由に設定でき、調査結果の集約、分析、アウトプットという一連の流れをパッとできるようなツールとして利用できれば、他のどんな業種にも魅力的な製品になると思いますので、期待しています。
下柿元様:
そうですね。また、COMPANY、特にCTMについての使用例や導入事例をもっとたくさん聞きたいですね。ユーザーコミッティというユーザー会もあるので、そこで多くの情報交換ができることを期待しています。
来年度から新たな中期経営計画がスタートするので、多くの新しいことに取り組んでいきたいと思っています。その中で大きな一つのテーマとして、色んなものの見える化があります。可視化された情報を従業員のキャリアビジョンに紐づけて、それに応じた成長機会や活躍の場を、私たち人事部門がしっかり提供していきたいです。
その一方で、やはり私たちは組織として生き残っていかなければならないので、従業員のキャリアも大事ですが、経営戦略とも連動していく必要があります。個人も組織も一緒に成長していけるよう考えていきたいと思います。
大迫様:
色んなものの可視化は、既存の従業員の長期活躍だけでなく、新卒や中途といった採用の面でも意義があると思うんです。上司の感想や気分で評価や教育が実施されるのではなく、データをもって診断している、つまり、一人一人を丁寧に見てくれる会社というアピールができます。会社にとって従業員数は分母そのものですので、とても大切なことだと思います。こうした活動の基盤としてCOMPANYが貢献してくれることを期待しています。

※本記事は2024年4月時点の内容です。
業種
従業員規模
関連する導入事例
お役立ち資料
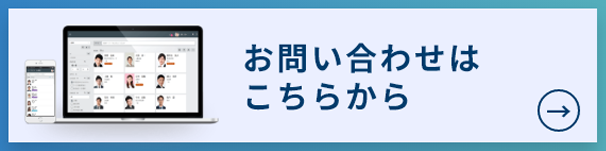
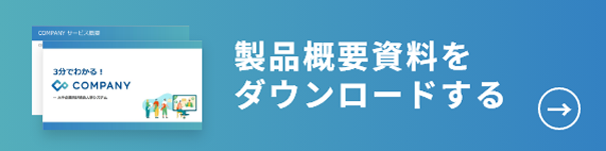

カテゴリから導入事例を探す
- 業種
- 従業員規模
- 目的・課題
業種
- 全て
- 陸運
- 輸送用機器
- 鉄鋼
- 製薬
- 小売・流通
- 公共
- 建設
- 教育
- 協同組合
- 化学
- 医療・福祉
- メーカー
- IT
- サービス
- その他業種
従業員規模
- 全て
- ~2,000名
- 2,001~5,000名
- 5,001~10,000名
- 10,001名~
目的・課題
- 全て
- クラウド化
- システム連携・一元化
- システム老朽化・使いにくさの解消
- スマホ・マルチデバイス対応
- ペーパーレス化
- 業務効率化・管理コスト削減
- 人材育成・キャリア支援
- 人事データ分析・可視化
- 多様な勤務形態の管理
- 適材適所の人材配置
- 独自制度への対応
- 変化に対する柔軟な対応
- 従業員エンゲージメント
- 過重労働の防止
- グループ会社のシステム基盤統一








